伝統論
野呂芳男
初出:『熊野義孝の神学』熊野義孝記念論文集刊行会、1986年、51-73頁)
※ 論文の転載についてご許可下さった熊野義孝記念論文集刊行委員会・椿憲一郎牧師に深く感謝申し上げます。
1
熊野神学における伝統論を取り上げるに当って、先すその特徴を浮彫りにするために、熊野先生も著書の中で言及したことのある、英国国数会の神学者オリヴァー・C・クウィック(Oliver Chase Quick)のある講演を紹介したい。そこに表現されている伝統論と熊野先生の伝統論の類似と相違とを指摘したいがためであるが、拙論はそのあとで、今後我々として考えなけれぱならないと思われる若干の問題点を示唆することとなる。併し、拙論の意図はあくまで、熊野先生の伝統論を理解するところにある。
取り上げたいクウィックの講演は、1922年に彼がニューヨークにある聖公会系のジェネラル神学校に招かれて行ったふところの「パドック司教記念講演」(Bishop Paddock Lectures)であり、修正加筆の後に『自由主義と近代主義と伝統(Luberalism, Modernism and Tradition)という表題の下に出版されたものである(1)。
カトリックであろうとプロテスタントであろうと、キリスト今日教信仰が旧新約聖書をその信仰の土台として据えていることとは改めて言う必要がないが故に、十八世紀以降の歴史科学が聖書をその対象として扱い、聖書記事の伝える事柄を他の書物同様に論じ始めた時には、当然のこと多くの信者の信仰生活が根底から揺振(ゆすぶ)られることとなった。こういう事態を、教会に対して信仰的にまた学問的に責任を負う教職や神学者たちが放置しておく筈がなかった。
高等批評と言われるところの、聖書に向けられた歴史科学的分析は、聖書記事の背後にある出来事に迫り、それを、それが生起した状況と共に客観的に把握しようとした。そして歴史分析は、キリスト教の起源であった実際の出来事が何であったか、その出来事がどのように人々によって評価され、解釈されて行ったか、また、その評価なり解釈なりが聖書記事が書かれるまでにどのように進展して行ったか、を探求した。勿論、正統主義によれば、実際の出来事と後の評価や解釈は断絶し難い一連のものであり、両者は互いに矛盾することなく、調和を保って教義にまとめられ得るものであったのだが、当時の高等批評は、この講演の中でクウィックが指摘しているように(2)、出来事と評価の間に大きな間隙を見出すこととなったのである。(今日はまた高等批評それ自体が大きく変容を遂げ、従って前述の事実と評価との関係に関しても、クウィックの講演の時からはかなり違った見方をされるに至っているが、当時の見方の正否に拘らずに、今は論述を進めることとする。)そして、新約聖書の中では正統主義が主張してきた程には事実として確認できる出来事は多くはなく、むしろ、事実というよりは後の評価なり解釈なりが作りあげてしまった事柄が多い、と高等批判は断言するに至っていた。
このような事情が、一体キリスト教とは元来何であったのか、また、その後の二千年のキリスト教史をも付加して考える時に、キリスト教の本質とは何であるか、という質問を人々の心に思い浮かばせるに至ったことは当然である。そこで、キリスト教本質論との絡み合いの上で、クウィックは上述の事実と評価とを、新たに総合しようとする試みに二通りあったと言う(3)。一つは、高等批評がこれ迄に正しいと確認したところの事実に限定して、そこにキリスト教の本質を見ようとする試みである。この試みから見ると、後に発展した様々の教理はことごとく誤りであり、純粋の福音を格下げするもの、不必要な神話である。もう一つの試みは、教理の発展を終始支えているところの諸観念にキリスト教の本質を見ようとする。キリスト教の起源とされている出来事それ自体というよりは、それを起点として生成してきたところの、歴史の進展、その進展を支えてきた人々の心に存在した諸観念を重要視するのである。
故カール.マイケルソンが東京滞在中に初めて熊野先生の思想に接した折、そのあまりにも西欧的な香りの立罩めているのに驚き、更に先生が一度も海外に学ぱれたことがないと知って驚きを倍加していたが、先生の著書に馴れ親しんできた者たちにとっては旧知の事柄である。それ故に、これ迄に述べてきたクウィックの講演の状況は、熊野神学の基盤となった状況である、と言っても誤りではないと私には思える。少なくともこの拙論の主題である伝統論は、熊野先生においてもクウィックと同じような状況を踏まえて形成されたものと考えてよいのではないだろうか。そして、私の見るところでは、両者ともに、二つの試みのいずれにも自己の立場を完全には一致させることができず、それぞれの試みに真理契駿の存在することを諒解して、それらを綜合して第三の立場とも言うべきものを作りあげている。このように両者が類似の神学的営みを行っているように思われるので、もう少しクウィックの講演に聞くことにしよう。
2
第一の試みを行ったのは、クウィックによると、自由主義的プロテスタンティズムであり、その代表者はアルブレヒト・リッチュル(Albrecht Ritschl)であった。よく知られているリッチュルの神学の大要をここに詳細に紹介する必要はないであろうが、クウィックの第一の試みに関する理解の仕方を我々が把握するためには、クウィックがリッチュルにどのように接近して行ったかを見る必要があろう。
クウィックは先す、リッチュルが認識論を三類型に分けたことをあげる。一つはプラトンのそれであり、現象と実在とを分けて前者は単なる欺き迷わす仮象であるとなして、認識の真の対象となるべきものは後者の実在であるとした。第二の類型はカントの認識論であり、プラトンと同様に現象とものそれ自体の間に断絶を想定するものであるが、プラトンとは逆に、我々が認識し得るものは現象のみであり、ものそれ自体ほ全く我々の把握を越えものとなした。第三の類型はロッツェの認識論であって、これはものそれ自体をその現象から切断することを拒否し、実在ほ我々の日常経験の中にその働きの効果をあらわすものとなした。リッチュルは第三の類型を採用して自己の思索の基礎となし、この観点から、伝統的な神人二性の一人格というキリスト論と離別したのである。
リッチュルの観点に立てば、伝統的キリスト論は.プラトン的な現象と実在との二元論に基礎付けられたものと見做され、何らかの神泌的体験によって我々は史的イエスという現象の背後に隠れている実在、即ち神の子たるキリストに迫らねぱならなくなる。このようにリッチュルの見るところでは、キリストにおける神性は神秘主義的な道によってしか到達できないものとなり、人性との結合は、実質なき主張、単に何らかの神的な方法で結合しているという主張に擁護されるだけになってしまったのである。ところが、プラトン的に言えば仮象であって実在とは比較にならない程に格下げされねばならない筈のキリストの人性が、神秘主義的な道を取れない大多数の信老たちにとっては実際的な関心事とならざるを得ない。それ故に、十字架とミサによって信者に与えられるキリストの死の効果は、ひたすらに人間としてのキリストより由来するものとなる。このようにして形而上学的な重要性は神性に、実際生活での重要性は人性に、という仕方で伝統的なキリスト論は二元論的に取り扱われてきてしまった(5)。
以上の如くにリッチュルによる伝統的キリスト論の批判を紹介した後に、クウィックはリッチュル自身がキリスト論をどのように積極的に展開したかを述べる(6)。ロッツェの認識論に立ってリッチュルは、人間イエスにおいて神の子たるキリストの神性の働きの効果を見ようとする。そして、周知のように人間イエスの崇高な道徳性と、イエスの教えた隣人愛に基づいた人類共同体としての神の国こそが、リッチュルにとっては神ヘ至る唯一の道となったのである。
神の父性と、神の子としての人間の兄弟性がイエスの教えの中心であり、イエス自身もその教えを実践したと考え、そこにキリスト教の本質を見たハルナック(Adolf Harnack)は、明らかにリッチュルのこの路線を進展させたものと言うことができる。併し、クウィックによると、ヘルマン(Wilhelm Hermann)はもう一つのリッチュルの強調点を継いだ。その強調点とは、いわゆるリッチュルの価値判断(Werturteil)であるが、これは神並びにキリストの本性を、それらが我々にどのような価値をもっているかに従って判断するものであった。このような価値判断は、キリストの神性を単に(我々の心の中にそれがどのような価値をもっかという)主観に依存させることとなるという、しばしば聞かれる批判に対しては、クウィックはある程度リッチュルを弁護する。我々がある色彩を見る時に、我々の見るという事態から色彩が完全には独立していないという事情があるが故に、色彩は全く主観的であると言うならば、それは間達いである(7)。併し、クウィックはこのような弁護の後直ちにリッチュルのような立場を追い詰める。キリストの人間性が我々に対してもつ効果であるところの、この神性は、イエスが我々の父として教えた神とどのように関係しているのであろうか。つまり、神と呼ぶ程に我々にとって価値あるキリストであるならば、何故にそれを一歩進めて、永遠に、形而上学的にキリストは父なる神と同質である、と言ってはいけないのか。勿論リッチュルやその弟子たちが、この一歩を進み得ないのは、その歩みが彼らの恐れるキリストの神性・人性の二元論的理解に舞い戻ってしまうからである、とクウィックは言う。
3
近代の科学的な高等批評が、聖書の証言する事実と、証言がなされた時に施されたところの、その事実に対する解釈や価値判断との間に、それまでは人々の意識に上って来なかったような大きな間隙があることを人々に認めさせるに至った折に、クウィックによるとそれに対応する二つの試みがあった訳であるが、その一つがこれまでに大略を紹介した自由主義フロテスタンティズムであった。クウィックは史的イエスにキリスト教の土台を置こうとした点で自由主義プロテスタンティズムを高く評価しながらも、イタリアの哲学者ルギェエロ(Ruggiero)やイギリスの教会史家フォークス・ジャクソン(Foakes Jackson)と同じ様に(8)、それがキリスト教は一つの生ける有機体であって、歴史の中を生長発展してきたものであることを忘却してしまったと言い、そこに自由主義プロテスタンティズムの弱点を見ている。
クウィックのこのような問題意識を私なりの比喩に言い換えるならぱ、点と線の問題であると言い得るかも知れない。史的イエスに一切を賭けた自由主義プロテスタンティズムの性格は、信仰生活の一切を史的イエスの事実という一点から引き出そうとしたのである。それに対して、クウィックがもう一つの試みとして紹介する、後述のカトリック近代主義(Catholic Modernism)は、キリストを出発点としてその後、歴史の中に有機体的にそれ自体を発展させてきた伝続、直線の如きものに信仰生活をすべて依存させようとしたのである。
カトリック近代主義の代表者としてクウィックが紹介するのは、あまりにも有名なジョン・ヘンリー・ニューマン(John Henry Newman)である。既に紹介したプロテスタント近代主義が、実証できるイエスの生涯に基づいてキリスト教の木質を探ろとしたのとは対照的に、ニューマンはむしろ実証できる事実よりも、クウィックの表現によれば「人々の思考の中にある」キリスト教の「理念的な基礎(idealistic basis)を示唆する(9)」のである。即ち、点的な史的イエスにすべてのキリスト教の教理や実践の責任を負わせることをせずに、むしろキリスト教を動的に成長するもの、それ自体を神学的体系や教会組織ヘと発展させて行くものとして捕えて、キリスト教とはどういうものであるかに関する諸理念が人間の思考の中で徐々に脹らんで行くものであると考えたのである。従ってニューマンのこういう考え方によれば、伝統を形成する集団の方が個人よりも当然優先されるべき信仰の担い手となる。
成程この点でクウィックが、ニューマンを自由主義プロテスタンティズムと対照させているのは理由がなくはない。既に我々も見てきたように、リッチュルにしたところで決してキリスト教の中にある集団的契機を無視した訳ではなく、例えぱ隣人愛に基づいた共同体としての神の国を我々の倫理的理想として掲げている。併し、キリスト教の「起源と伝統とは、全体」としてのキリスト教「に、そのすべてをつくして貢献しなければならない(10)」と主張し、しかも基本的なものとして把えられたカトリシズムに、プロテスタンティズムの原理は従属しなければならないことを主張するクウィックにとっては、プロテスタンティズムは矢張ニューマンと同じように映ったのであろう。即ち、一人々々の心の中に同一のもの(福音信仰)が繰り返し作られて行き、それらの人々が集まったものが救会であると主張するところの教派としてである(11)。
ところが、クウィックが言うように、ニューマンの立場は伝統の真理性を、その伝統を支える歴史的事実なしに承認するに至る危険なしとしない。遂には新約聖書に記された諸事実に結び付けている舫(もやい)を解いて、船がその時代の潮流に浮ぴ流されて行く事にもなりかねないのである(12)。
クウィックの見るところでは、上述の危険を心配しなければならない方向に歩み始めたのがアルフレッド・F・ロアジー(Alfred F. Loisy)やジョージ・ティレル(George Tyrrell)であった。一例をあげて、この点を明らかしておこう。ロアジーの著名な書『福音と教会』(※L Evangile et L'Eglise)は、ハルナックの『キリスト教の本質』(Das Wsen des Christentums)ヘの批判の書とも言うべきものであった。ハルナックがキリスト教の本質を、彼が信憑性を実証できると考えた史的イエスの教えに求め、神の父性とそこから流れいずる道徳性とした事は前にも述べたが、ロアジーはこれを批判するに当って、ヨハネス・ヴァイス(Johannes Weiss)やアルバート・シェヴァイツァー(Albert Schweitzer)などの徹底的終末論の立場に身を置いたのである。
周知のように徹底的終末論においては、ユダヤの民衆により、きわめて間近な出来事として神の国の到来が待ち望まれていた、とされるのである。その折には人の子という存在が天より遣わされて、奇蹟的に神の力によって地上に神の国が実現する。イエスも間近に来る筈の神の国を信じ待ち望んでいたのであるから、その教えた倫理は、神の国の来臨までの僅かな期間だけに有効性をもつものであって、ハルナックが主張するように、そこにキリスト教の本質を求めるようなものではない。むしろキリスト教の本質はイエスの説いた神の国の理念にある。
そうすると、明らかにイエスの期待した神の国は来臨しなかったが故に、イエスは誤った幻想のために身を賭した熱狂者ではなかったか、というような質問が、当然ロアジーの立論に向けられると思うが、クウィックはこの点で。ロアジーにきわめて同情的である(13)。神の国がイエスの期待した通りの形態で、予想した時に事実来臨したかどうかが重要な事柄ではなく、イエスがそういう期待と表現の中に盛りこもうとしたところの理念、とてもそこに盛りこめなかった程の雄大な、普遍的な人類の愛の共同体という理念が重要であった。これは旧約聖書の中心を流れてイエスに到達したものであり、更にイエスの後も生長して行くべきものであった。イエスと全く同じ形態においてではないにしても、カトリック教会こそは、この神の国の理念の進展なのである。これがクウィックの弁護するロアジーの思想である。
併し、ロアジーに関するクウィックの弁護は、ロアジーを正当に評価すべきであるといクウィックの公平感覚に由来するものであって、彼がロアジーの思想の一番の弱点を衝くのを妨げない。ロアジーの理論は、歴史の進展のどの状況をも神の名によって是認することになりかねない。これは別の道を通ってではあるが、自由主義プロテスタンティズムと同様に、その時の個人の主観的信念によって、どのキリスト教の状況が本質であるかが決定されかねず、うっかりすると現状のすべてが神の業として承認されることともなる。ヘーゲル哲学のように、歴史の底に流れる汎神論的に神的なものが構想されることともなり得る。従って、カトリック近代主義の道は、錯綜する歴史の諸潮流のどれが真理であるかを最終的に決定する唯一の権威を要請せざるを得なくなる(14)。
さて、我々はここでクウィックの講演がこの後どのように展開されて行くかを追うことを一応止めて、結論的にクウィックがどのよyな態度を以上の二つの試みに対して取ったかを述べて先を急ぐことにしよう。但し、重要な点にはまた戻ってくることにしたいのではあるが。
点と線との比喰を用いるならぱ、クウィックのとった態度はどちらかというと線の方を重視したものと言えるであろう。ローマ・カトリシズムのように、伝統の錯綜する諸潮流の中から真理をえらぶに当って、それをローマ教皇という至上の権威に委ねてしまうことは、当然のこと聖公会の神学者であるクウィックのよしとすることではなかった。併しながら、各個人の魂がそれぞれ孤独に神に接して福音を信じ、そういう信者たちが集合して教会を作ると考えるよりは、クウィックはもっとカトリック近代主義に近付いて、集団の方を個人に優先ざせ、集団の交わりの中で個人はキリストを信じるに至るとなした。そして、クウィックにとってその集団を一つの有機的なコイノーニヤたらしめるものは、神・人二性の人格たるキリストの権威であった。つまり権威は地上のペテロの後継者というようなものでなく、点的にポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架上の死を経て、復活して、線的に今も霊的に教会を支配するキリストである(15)。従って、クウィックの伝統論はニケア・カルケドン公会議のキリスト論のあとを受継いでおり、史的イエスという点への固着というよりは、それに関する信仰告白から生れてきた理念と体験という線的なものが土台となっている。
4
幾分なりとも態野神学について知る者は、これまでに述ベられてきたクウィックの伝統論に相似の諸点が存在することに気付くであろう。態野先生にとってキリスト教は、「歴史という衣裳を既に着けた我々宗教(16)」であり、永遠者の肉体とも言うべき教会を他にしては、その本質を探る手段はない。永遠と時間とが終末論的に死の向う側とこちら側という仕方で質的に区別された上で、ニケア・カルケドン公会議のキリスト論が、教会という受肉のキリストの身体の(時間的)延長の中での伝承を形造り、信者はこの伝承に依拠して、復活の希望をもちながらこの世の生をおくる(17)。
興味深いのは熊野先生がニューマンの「歴史に深入りすることは、プロテスタントをやめる事だ」という言葉を引用し、これに好意的である事実である。ニューマンのこの言葉によって、熊野先生はニューマンが、キリスト教である以上は教義が必要不可欠であり、しかもその教義とは根本的な伝承を指す、と主張したと見ている。根本的な伝承とは普遍的に初代の教会によって受容されていたところのものであり、当然のこと今日に至るまで歴史の中を貫き、続いてきたものである(18)。
換言すれば、ニューマンの言葉の引用によって、態野先生にとってはキリスト論の古典的教義を無視したとしか考えられないリッチュルやハルナックのごとき近代主義的プロテスタンティズムを排撃したのである。熊野先生にとっては、このような公同の教義を伝承してきた「敦会の外に救いなし」なのである(19)。
併し、伝統という言語によって通常我々が想像するのは、歴史のある時期に形成されて、そのあとは変化しないままで我々の手に譲り渡されてきたもの、固定した、静的なものである。この事情にほ熊野先生も気付いており、主張する伝統は常識的なものではなく、動的伝統であると言う。そして、伝統が動的なものである理由は、それを受容する者が人格的に受け入れるからであって、そこに伝統が本質を変えないままである程度の時代状況ヘの適応をなし得る根拠がある。即ち、伝統を形造りそれを次の世代に譲り渡す歴史的社会があり、それを受け取るところの、次の世代に属する歴史的社会、その中に生きる個人がある。個人はいつもこのように歴史的杜会と切断し得ないという思いを込めてであろうが、熊野先生は、人格的存在はいつも、個別なる実存であると共に集合的一人格(Gesammtperso※nlichkeit)である、とう(20)。ここでも熊野先生の強調点はむしろ後者にあり、やはりクウィックと同じように、集団が個人に優先しているのである。
他の宗教にとってもそうであるが、特にキリスト教にとって伝統論が中枢をなしているのは、信仰の規範であり、キリスト認識の源泉である聖書が、既に伝統によって形造られたものであるからである、と熊野先生は言う。新約聖書は旧約聖書の伝統を前提としているし、また旧約聖書はイスラエルの父祖たちの伝承に拠っている。従って、旧約聖書の伝統が、キリストの啓示に接した上でその伝統の中に生きる人々により、解釈されて作られたものこそ新約聖書なのであり、聖書解釈は既に聖書の中で最初から教会的になされたものであった(21)。このように主張することによって、ニューマンとは異なり明確にカルヴァン主義に立脚する熊野先生は、根源的な伝統として聖書を我々に指示し、種々の伝統の流れの正否を判断する権威として聖書を置く。
聖書はまたそれ自体を指し示さずに、我々に対して生けるキリストを指示する。即ち、聖書文書の作者たちは、我々と同じように伝統の中に浸り、教会の中でキリストを礼拝しながら証しの文書を書き残した。従って熊野先生によれば、我々は聖書に、サクラメントや教職制を考慮しないで、接近してはならない、ということになる(22)。では何処がローマ・カトリック教会の伝統論と異なるのか。熊野先生によると、ローマ・カトリック教会の伝統の中には、キリスト教的というよりは一般宗教的諸要素や、ギリシアの形而上学に由来するものなどが多分に伝えられており、それらは聖書の伝統と質を同じくするとは言い難い。そのため、ローマ・カトリック教会では信仰の権威として、聖書と伝統という二重のものを定立せざるを得なくなっている。ところがプロテスタント教会にとっては、聖書が我々の伝統であって、聖書即伝承でなければならないのである(23)。
ところで、『基督教概論集』(全集第六巻)の140―141頁は、私には特別の注意を払わねばならない所のように思われる。ここで先生は、伝統というものが本来その中に生きる人々にとって具体的に、身近なものとして実感されるものである以上は、伝統が形成された場所と時間とに当然束縛されたものでなけれぱならないが、このことは普公性と一見矛盾しているように思われる、と言う。誤れる伝統主義とは、局所的・時間的である伝統の相対性を忘れて、ある時期、ある場所で形成されたものをいつでも何処でも通用するものの如くに振舞うものである。こういう伝統主義と区別されなければならないことは勿論であるが、普公性は、前述の相対的なものとして把握された伝統とも(熊野先生においては)異なるように思われるのである。と言うのは、「普公性は不可視的永続的でありそれに対して可視的時間的な連続として伝統が把握される。伝統はよしそれが永遠者の足跡であるにしても、ただちに不可視者の映像ではなく、それ自身が肉体的存在でなければならぬように想われる。否、精神的肉体的二重性に於ける連続として可視的感触的な存在でなければならぬ(24)」からである。つまり、福音という永遠の真理が我々の所に届くためには、どうしても具体的な時間と空間――たとえば原始キリスト教会のような――を纒〔まと〕わねばならない、と先生は言う訳であるが、その後で読けて「伝承の普公性とは、それ故に、具体的には必ず局所的時間的な存在と結ぴついて可視的感触的な伝統を形成するものの如くである」と言う。
熊野先生も今引用した文章の中では、伝承と伝統とを区別し、前者を普公的なもの、後者を、前者が受肉した局所的時間的なものとして書いている。先生の場合、伝統と伝承とは大体において区別されて用いられてはいない。今引用した文章の三、四行あとではすぐに「伝承ないし伝統」という文句があって、そこではもう既に区別は失われてしまっている。併し、この箇所での伝承と伝統との区別は、あるいは熊野先生自身が気付かたかった程に熊野神学の本質を表現していると思う。もう少しこの区別が生々としている文章を引用してみよう。「しかも伝統はいわゆる伝統主義たるにとどまらず、不断に自己生命の発展を背負い、伝承の解放を促す。客観化された伝統はつゆに主体的生命としての伝承的活動を要求する。そして伝承の本質はそれの無限界性ないし普公性に見出されるという(25)」。
以上の引用から明らかな事は、この箇所の視点から考察すると、熊野神学における伝統とは、普遍的な伝承がある時期、ある所で具体的になったもので、伝承の受肉と言ってもよいものとなろう。そして、伝統はいつも伝承を必ずしも正しく受肉させているとは言えないものであるが故に、その誤差を伝承によって正されねばならないのである。唯、ここで我々が注意しなければならないのは、既に述べたようにニューマンがキリスト教の本質を歴史の中に進展する諸理念と見たのだが、熊野先生が「普公性は不可視的永遠的である」と言った時に、それと同じものを意昧したかどうかである。「不可視的永遠的」なものというと、何か理念的な感があるが、ニューマンと違って熊野先生の場合には発展して行く理念でほなく、ロゴスのイエス・キリストへの受肉であゐことは言うまでもない。そうすると、普公性とは、イエスの受肉をめぐる教義であることは言うまでもない。そうすると、普公性とはロゴスの伝承をめぐる教義であることとなり、この伝承(普公性)を更に時代と場所との中ヘ受肉させたものが伝統ということになる。
内容的には伝承とはニケア・アルケドン信条に表現されている三位一体論とキリスト両性論であり、これらは熊野先生によれば、遡って言えば聖書に還元されるものであるが、近代の方向ヘ延長すれば宗教改革者たちの信仰義認論(宣義論)となる(26)。熊野先生にとっては、ルターやカルヴァンの義認論は伝承に何か新しいものを付加したのではなく、あの時代でのキリスト両性論の正しい解釈であった。
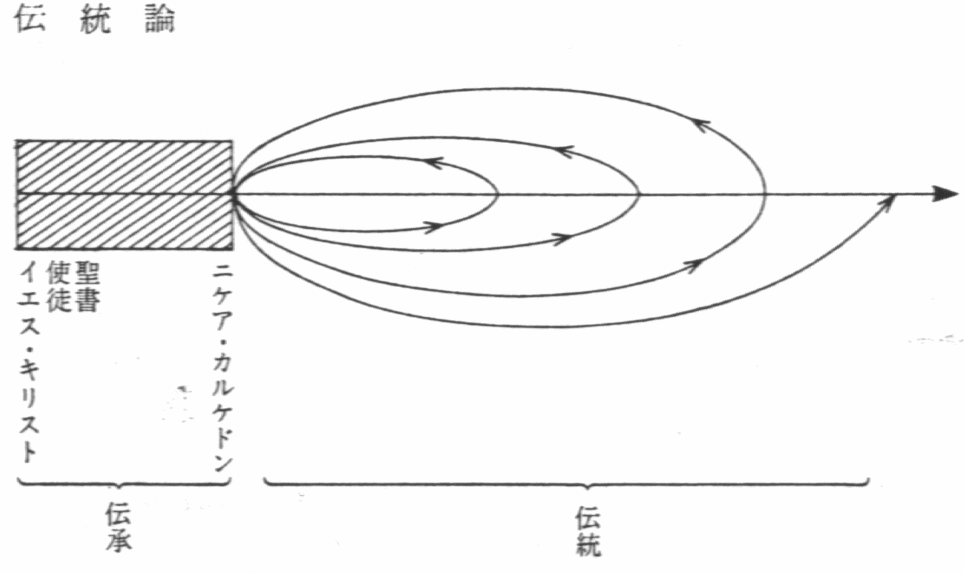
これを図示すれば上のようにでもなろうか。伝統はいつも伝承に立ち返りながらその誤りを正しつつ、しかも必ず再びそれ自体を創作的に時の状況に受肉させて行かねばならないのである。そして、この伝承の中には、ローマ・カトリシズムやアングリカン高教会主義の使徒伝承の理解と違い、「使徒的たるは単に使徒の伝説を継ぐというのではない、使徒によって代表せられた教会的宗教的権威の伝承をいう(27)」との考えも含まれている。
5
既に自由主義プロテスタンティズムをイエス・キリストという一点に集中したキリスト教ヘの接近とし、カトリック近代主義を伝統という発展的な直線でキリスト教の本質に接近しようとしたものと私は喩えてみたのであるが、熊野神学の場合には点と言うよりは若干の長さをもった伝承と、その伝承を受肉させる伝統との緊張を妊んだ開係、伝承を受肉させつつ、いつも伝承によって裁かれる関係であると言ってもよいであろうか。そして、このような考えが、矢張ニケア・カルケドン信条のキリスト両性論を土台としてニューマンの歴史の中に進展する伝統という思想を生かそうとしたクウィックと、多くの点で共通したものをもつことは既に指摘した如くである。
クウィックが自由主義プロテスタンティズムの代衷者として講演の中で取り上げたリッチュルやハルナックは勿論熊野先生によってもしばしば取り扱われているが、クウィックによっては時間的制約のためか言及されていなかったシュライエルマッハーが、熊野先生の場合にはむしろ自由主義的プロテスタンティズムの代表者としてどの書物にも登場することは周知の通りであるけれども、自由主義プロテスタンティズムヘの批判においては、熊野先生も大体クウィックと揆を一にしている。そこでは歴史的イエスが誇張されて、イエスの神人合一的な体験の感化に我々が浴することが信仰と見做されており、そのような感化を与えるところにイエスの仲保者たる性格がある。我々の倫理的精神こそが大切なものなのであって、それがたまたまイエスという歴史的事件により触発されるのである。つまり、人間一般に性来存在する神的なものが、イエスの倫理性に刺戟されて顕在化してくるのであり、熊野先生の見る所では、結局こういう自由主義プロテスタンティズムは汎神論的なものなのである(28)。
前に熊野先生がニューマンについて述べた所を私は紹介したのであるが、実は熊野先生によるニューマンについての言及はそれ程多くはないのである。恐らく熊野先生に、歴史の中で具体的に展開するキリスト教の容姿を通して、その本質を現象学的に探ろうとさせたのは、ニューマンソと言うよりも(他の学者たちの影響もあったであろうが)何と言ってもエルンスト・トレルチ(Ernst Troeltsch)の業績ではなかったか。どうもそう思われる。熊野先生とトレルチとの関係については他の論文が予定されているようであるから、私は見過ごして行くこととするが、キリスト教という歴史現象の中にその本質を直観し、それを理念的に再建しようとしたのがトレルチであった。「本質直観の相手は、歴史に内在するキリスト教の生命ないしその理想にほかならない(29)」というトレルチに関する熊野先生の言及に接する時に、クウィックにおけるニューマンの役割が、熊野先生においてはトレルチによって果された事は、私にほほとんど疑いの余地がないように思える(30)。
どなたによってなされた発言であるか残念ながら明らかでないのであるが、ある時に、熊野神学はトレルチとバルトの綜合を志したものであるとの評価を伺ったことがある。これは熊野神学をよく知っている方の発言であると言わざるを得ない。少しく大雑把な言い方をすれば、熊野神学は伝承論をバルト、伝統論をトレルチとの接触によって得たとも言い得るのではないであろうか。そして、ニューマンのように伝統の正否の判断を最終的にローマ教皇に求めるような立場や、トレルチの如くにキリスト教を究極的に他の世界宗教と同じような相対的権威しかもたない、他とならぶ一宗救であるとする立場から、熊野先生が距離を保ったその姿勢が、先生のバルトへの共感の中に見られる、と言える。
ニューマン、クウィック、熊野先生のように教会の伝統を重視する立場は、既に述べたようにどうしてもその正否を判断する規準、あるいは権威を求めることになるので、神学が権威ヘの服従という形態を帯ぴてくる。熊野先生の場合には権威が伝承であるのだが、バルトヘの共感にも示竣されているように、伝承の理解はきわめてカルヴァン主義的である。同じように神人二性二人格のキリスト論に土台を置いていても、熊野神学にはこの点で、聖公会のクウィックから、性格上の大きな相違が見られる。伝承は福音の受肉したものであるが、その福音の理解が熊野神学においてはカルヴァン的であり、至上の権威をもつ主権者、人格的な絶対者が中心に立っている。
カルヴァン主義的な人格神が強列に刻印されているためと思われるが、熊野先生は伝承や伝統を喩えるのに人間の身体を用いるのであり、この点は全く独特だと言わざるを得ない。勿論、聖書の中でさえも教会はキリストの身体に喩えられているのであるから、身体の比喰が伝統に当てはめられることに不思議はない筈であるが、併し、寡聞の故か、熊野先生のように身体の比喰を伝統にあてはめて前面に押し出した神学者を私は知らない。これは神が人格的に考えられていることと、相即しているものと思える。人格神は擬人的概念であるので、その擬人法を正面に押し立てれば、神(あるいはキリスト)の身体という擬人法的概念が矢張りその文字通りの意昧に接近した形で使用されるに至る。「歴史的なるキリスト教はまた、その歴史的たるゆえに必然的に自己に纒いついている夾雑物を不断に整理し、ちょうど人体が栄養を摂取すると共に残滓物を排泄してゆくように、一個の生命体としてわれわれの宗教もまたそのような経過を辿る」と言われたり、「由来、生命的な伝統は自己の内部に喰い入って来る具質的なものとの格闘によって自身を形成して行くものである。健康な身体があらゆるものを飲食しつつこれを消化して自家の栄義となすように、時には不消化物を征服することによってなおさらに健康を増進するように、教会もまた時代と環境との諸思想、諸習俗に接触しこれらを摂取しながら具質的なものを同化していくのである。生理的な常識になぞらえて言えば、そのとき必要な仕事は、消化と排世とでる(32)」と言われる時に、我々はこの事情を察することができよう。
熊野先生にとって歴史とは人間が創作するところにその意昧をもつ。単に過去に何が生起したかという知識の集積が、歴史の本質ではない。歴史は人間の行為の場であり、人格的存在たる人間は自覚した自分の使命に応じて、そこで行為し、小範囲と雖〔いえど〕も歴史の方向付けを変え得るし、また新しい歴史を創作する(33)。もしそううであるならば、我々は一人物の歴史の中での行動を通して、ある程度その人物の本質を見通し得ることになるであろう。私にはこういうような思考が、トレルチと折衝しながら伝統論を形成しつつあった熊野先生の心を横切ったのではないかと思えて仕方がない。人格的な神を知るには、神が作る歴史、特に教会の歴史を見ればよい、という訳である。そして、歴史は人格が反映する場なのであるから、その真理も、自然の真理を求めるような仕方で、即ちそこにあるものを眺めたり手で触れてみるという仕方で得られはしない。丁度一人の人間がもう一人の人間を個別的によくよく知り抜いて初めて、我々が普遍的な人間の喜ぴや悲しみを知ることができるように、歴史の真理は個別の中に深く沈んで行って普遍ヘ突抜ける道によってしか知られないのである。それ故に、人格的な神の働きに推進されて歴史の中を生成するキリスト教の絶対性の如きも、沢山の宗教と共にキリスト教をそこに並べて、すべてを自然物の如くに観察し比較検討したところで明らかになるようなものではなく、個別的なキリスト教の伝統の中にすっぽり身を沈めて、自己の奥底にある普遍的なあるものが、そのキリスト教伝統を形成する神との出会いを体験し、これでよしと納得する自分の表面に浮ぴ上って来てこそ、知り得るものなのである。「人格的生成という徹底個別性と究極的普遍性との矛盾統一の場面に在って、初めて宗救の真理とその絶対性とが認識把握される(34)」のである。
人格的存在は言葉によって自己の意志を伝える。神もそうされたのであり(35)、その言葉がキリストの出来事であるし、その受肉が伝承、伝統なのであるから、伝統に接したからといって誰でもが信者になる訳ではない。言葉は応答を待つものだからである。伝統から自然神学を作ることはできない。人がどれ程に自己を語ってくれて、その物語がその人物の行動の意昧をある程度照明してくれたとしても、人間にはいつも他者には窺い知り得ないところが最後まで残るものであるが、熊野先生にとっても人格的な神は啓示の神であると同時に隠された神である(36)。
啓示とは別に、多数の宗救の中を流れる普遍的宗教性(宗教的アプリオリ)などから神を知ろうとするのは、一種の自然神学であろうが、熊野先生はこのようなものを一切拒否してキリストにおける啓示のみに固着する。むしろ先生にとって、宗教的アプリオリというようなものは汎神論的な神観に由来するもので、キリスト教の人格神と矛盾する。従って熊野先生によれぱ「ひとは生れながらにして汎神的で」あるから、「われわれの道は」そういう汎神論的宗教的ア・プリオリの産物たる「神からの、宗教からの、解放であるとも言える(37)」のである。つまり、熊野先生にとっても宗教はバルトの言う如く不信仰の業ということとなる。
カルヴァン主義的な主権者なる神が自己を啓示する時に、それが人格的な啓示であるか故に、言葉によるものとなる事は前述した通りであるが、熊野先生によると、我々が人格的存在たる神と出会って初めて、人格の奥底から神の言葉によって呼び出され、応答を迫られて真に深みのある人格存在となり得るのである。「啓示は権威ある命令者の面前にわれわれの人格を引き据える(38)」。このようにして真に人格神の前に立たされた者は、強烈な応答ヘと駆り立てられるが故に、「告白者は時に殉教者でなければならぬ(39)」し、神によって罪赦されたという深刻な信仰体験こそが「猛烈な道義心を産み出し、……罪人が天使の如くに化し得たという教会史的実証に訴えねぱならぬ(40)」のである。
教会史的実証として恐らく熊野先生の頭脳に去来したものは、トレルチが研究し賞賛した、あの十六世紀及び十七世紀のカルヴァンやカルヴァン主義の形造った光栄ある歴史であったであろう。そのような光栄ある歴史に裏打ちされているという自信があったから、熊野先生は教会の作り上げた文化たる「厖大な現象的実存よりして永遠者の事業の意義を汲み出(41)」そうとしたのである。更に熊野先生にとっては道徳的実践こそが、世の人々が問うところの、信仰のみによる救いという福音によって本当にキリスト者は文化的責任を全うし得るのか、という質間ヘの答であった(42)。このように信仰によって義とされた者の道徳生活や、教会の文化面での誇るべき活躍などが、それによって神の前に義とされる行為としては勿論のこと、義とされる信仰に付加されるべきあるものとも、熊野先生によって見なされてはいない。そのことは諒解できるのであるが、併し、このような文化現象の取扱いの中に、私は十七世紀のカルヴァン主義者が、自分が救いに予定されていることの保証を、自分の生活の聖化の中に求めたのと同じ態度を見ざるを得ないのである(43)。
6
残った紙数を、熊野神学の中で今後我々が考えて行かねぱならないど思われる、二、三の点を指摘することに費したい。
? 熊野先生は今日の我々が十七世紀になされたような形式で予定説や自由意志論を論ずることの愚を指摘される(44)が、併し、そのような古ぴた形式の議論の中に盛られている真理は尊重されねばならないと教える。神の恩恵のみによって救われるという事実の徹底は、「信仰は絶対者の行為を映すものであって、それ故に空洞の如き場所でなければならぬ(45)」と言う言葉を熊野先生から引き出す。ここでは元来「我―汝」という形での神と人との人格的な関係が、神は空洞を満たす水や空気に、人はそれを満たされる空洞というように空間的象徴に置きかえられてしまっている。空間的象徴を土台にして考えれぱ、人間の方が神の方ヘ一歩でも出掛ければ、それだけ神の方からの歩みを削りとることとなり、そういう態度は神の恩恵の絶対性を否定する神人協力説であるとして簡単に片付けられてしまう(46)。併し、この点はもっと考えてみる必要があろう。
人間と人間との関係に例をとってみれぱ、強烈な主体的自由の追求が、その努力が全く無なるものの如くに感じられるような他者からの受容、あまりにも有難い受容であるが故に、それまでの努力は全くそれを獲得するに役立ったものとは感じ得ない他者からの受容があり得るのである。空間の次元ではなく人格の次元では、神の絶対的恩恵の充足的完結性と人間の主体的な自由による神ヘの努力とは相反するものではなく、逆説的統一を形造る。そうでなけれぱ伝道も説教も教会形成の努力も必要がなくなる。熊野神学の神の人格性の強調は、こういう所で空問という別の次元に移行する必要がないのに、それをしてしまっているのではないか(47)。
? 今述べた空間的象徴を使用しての神と人間との関係の理解は、伝統論とそぐわない。もしも人間の信仰が空洞の如きものであるならば、神の言葉がイエスに受肉し、キリストの福音が伝承に、伝承が伝統に受肉する時には、そこにはもはや修正を要しない程の正統主義が形成されていなければならない筈であり、誤って錯雑している伝統を伝承に基づいて正そうとの戦いもない。教会は空洞の聖なる空間、また領域となる。併し、そうではなく世俗性は教会の中心まで食い入っているが故に、救会はいつも社会科学的にも批判されて行かねばならないのである。
熊野先生がトレルチに多くを学ぱれたことは、ご自身既に私が述べた事柄に気付いておられた証拠かとも思うが、教会の文化の領域での業漬や信者の日常生活を、信仰の正しさを証拠立てるものとして利用されるのはどうであろうか。神学は首尾一貫した学であって世界観と違うということが、繰り返されている先生の主張であるが、信仰の正しさとの関係で文化や道徳生活を引き合いに出すのは、例えばカルヴァン主義と資本主義との関係を、逆に今日の西欧主導の資本主義丈化の悪の根源として引き合いに出された場合、泥試合を行うもとともなろう。むしろ自然神学をはっきり認めて、神学と、理性による世界観(社会科学の如き諸科学を含む)とを、領域を別にしつつも相互に影響し合うものとした方がよいのではないか。そのようにすれば例えば社会科学の領域の問題としてカルヴァン主義の功罪を論じることとなり、いきなりそれに信仰の正しさを幾分なりとも依拠させるような神学上の論議を展開しないですむのではなかろうか(48)。
? 神と人間との関係が空問象徴で語られてしまうと、キリスト両性論における人間イエスの主体性が重視されず、神の働きの道具になる。こういう立場でも人問イエスが科学的な歴史研究の興昧ある対象であることは認められるのであるが、併し、史的イエスに関する研究の成果が、キリスト論に影響をもつことはない。この点に私は、同じようにキリスト両性論にキリスト教の本質を見たクウィックと熊野先生との相違を見るのである。人間は被造物であるし罪人なのであるから、クウィックにとっても勿論のこと、神と人間とは本性が一つではない。併し、神は人問を創造されたあと、人間と断絶を保ち続けた訳ではなく、人間の罪にも拘らす人間の中に働き続けている故に、未だ神を信じない人間であっても、その人間が隣人と愛において結ぱれる時には、そこに我々は神の働きを見得る。人問が共同体志向的な愛に生きる時に初めて、自分が本来の自己を目指す道を不十分ながら歩み始むたと感じ得るのは、このようなキリストに救われる前の神の恵みの働きがあるからなのである。人問は、この神の働きに支えられて自由であり、強制されずに主体的にキリストの所に来る(49)。これはアウグスチヌスなどの教会教父に見られ、聖公会の伝統にも融け込んでいる先行の恩恵(gratia preveniens)の思想であり、アルミニアニズムであると私は思うが、人聞イエスも我々と同じようにこの恩恵に支えられて神を愛し抜いたのである。キリスト両性論は、そこで神と人間との関係がもっとも正しく把握されねばならない場であるが故に、神と人問イエスとの関係がそこで飽くまで我―汝の人格的な閲係と考えられないならば、我々と神との閃係もそうではなくなる。神のみが働くという主張は、うっかりすると人間の主張や行動が神に満たされてなされたところのものとなり、絶対化される恐れなしとはしない。
? 神の啓示を人間が受領する場合でも、受領する側の人間が啓示を理解できるように――環境その他の条件上――されていなければ、啓示は無駄になってしまう。神の子の受肉も時が満ちるのを待たねばならなかった。ルドルフ・ブルトマンの言う前理解(Vorverst※ahntnis)をもう少し拡大し、社会学的な視野などを大幅に取り入れた上での世界観的・自然神学的な思索が、啓示を受領する側としての人問理解に必要であると私は考えているのであるが、啓示と受領する人間との関係は何も今に始まったことではなく、既に聖書においてそうである。イエスの使徒たちも当時のユダヤやローマにあった種々の宗教的・政治的条件の中で啓示を受領したのであるから、彼らの生活にまとわりついていた啓示とは思えないものまで、我々が啓示とする必要はない。ブルトマンの非神話化論以降この問題が初めて出てきた訳ではなく、まさに熊野先生の神学の出発点で既にその問題が解決急務のものであった。
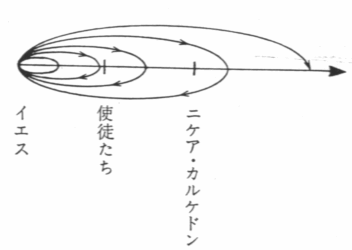
最近の聖書学などの結果を踏まえてみると、熊野先生が、イエスからニケア・カルケドン会議のキリスト論までを変らざる伝承とされたのを、もう一度点と線の比喩で上図の如く、その伝承さえも啓示の理解から理解され直すべきであると考え直してみる必要はないであろうか。
注
(1) Quick, O. C. : Liberalism, Modernism and Tradition, London, Longmans, Green and Co., 1992.
(2) Ibid., p.2.
(3) Ibid., p.3
(4) Ibid., p.6
(5) Ibid., p.7-8
(6) Ibid., p.8f.
(7) Ibid., pp.13-14.
(8) Ibid., p.24.
(9) Ibid., p.29.
(10) Ibid., p.150.
(11) Ibid., p.30.
(12) Ibid., p.31.
(13) Ibid., pp.33f.
(14) Ibid., pp.39-49.
(15) Ibid., pp.126f.
(16) 『熊野義孝全集』第六巻 東京、新教出版社、1976年、9頁
(17) 同上、253-254頁
(18) 同上、143-144頁
(19) 同上、103頁
(20) 同上、144頁
(21) 同上、130-131頁
(22) 同上、134-136頁
(23) 同上、133頁
(24) 同上、141頁
(25) 同上、141頁
(26) 同上、204頁
(27) 同上、138頁
(28) 同上、174頁
(29) 同上、64頁
(30) 熊野先生のトレルチに対する態度は著書『トレルチ』の他に、次の箇所を参照されたい。『熊野義孝全集』第六巻 35、63-66、69以下、72-73、91-93、268-271頁など。
(31) 『熊野義孝全集』第六巻、84頁
(32) 同上、148-149頁
(33) 同上、269-270頁
(34) 同上、75頁
(35) 同上、315頁
(36) 同上、312-313頁
(37) 同上、330頁
(38) 同上、315頁
(39) 同上、246頁
(40) 同上、237頁
(41) 同上、7頁
(42) 同上、227頁以下
(43) 拙著『ウェスレーの生涯と神学』、東京、日本キリスト教出版局、1975年、541頁以下
(44) 『熊野義孝全集』第六巻、253頁
(45) 同上、168頁。また、164-169、180頁を参照のこと。
(46) 同上、197頁
(47) 拙著『実存論的神学』東京、創文社、1964年、82-83頁を参照されたい。
(48) 拙著『神と希望』東京、日本基督教団出版局、27頁以下を参照されたい。
(49) Quick: op.cit., pp.131ff.
入力: 岩田成就
2002.9.18