Home > Archive / Bibliography
女神信仰と『ピノッキオの冒険』
野呂芳男
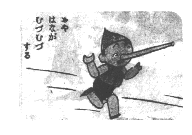
物語の著者と背景 / カトリック教会とピノキオ物語 / 森の妖精と観世音菩薩 / 神の偉大さとは / キリスト教はアニミズムとどのように関わるべきか / 人形療法 / 運命の神ゲマトリア / ピノキオの主体性 / キリストの十字架は生きることの否定ではない
初出:「女神信仰と『ピノッキオの冒険』」『黎明』第5号、松鶴亭(出版部)、2001年、LXI-XC頁。 (挿画は『ピノチオの冒険』橋本明夫訳、二葉書店、1946年より)。
物語の著者と背景
世界中の人々によって愛読されてきた木製人形ピノッキオの物語は、フローレンスに近い小さな村で1826年に生まれた。本名カルロ・ロレンツィニ(Carlo Lorenzini)というイタリア人によって書かれた。彼は筆名を、自分の生まれた村の名称から取ってコロディ(Collodi)としたが、著作を自分の職業とするまでには、兵士や政府職員や新聞編集者であったりした。彼を有名にした子供向けのいくつかの物語は1859年以降に書かれたものであり、彼が著作に専念し始めた後の産物である。彼は1890年に死んだが、彼が書いたものの中でも『ピノッキオの冒険』は多くの言語に翻訳されて、今でも子供たちを引きつけて離さない。
この書物は日本でも多数の翻訳があり、また、美しい絵本となって親しまれているが、コロディの文章を直訳したものは案外に少なく、翻訳者が自分の興味に従って物語の展開を変えてしまったり、抄訳したり、原本にはない物語が付け加わっていたりする。私の知る限り、唯一原文をそのまま日本語に翻訳したものは、杉浦明平氏によって訳され、岩波少年文庫の1冊として1958年に出版されたものだけである。この事情は日本だけの現象ではなく、英語の翻訳を見てもその通りであるが、キャロル・デラ・チエサ(Carol Della Chiesa)が翻訳し、アツティリオ・ムシノ(Attilio Mussino)による見事な挿絵を添えて、1927年にマクミラン書店が出版したものやハーデン(E.Harden)によって翻訳され、1974年以降イギリスのパフィン・クラシックス(Puffin Classics)によって出版されているものは、原典の忠実な翻訳である。
物語の初めは原典では
「何世紀も前の昔のことですが、あるところに住んでいたのは……『1人の王様でしょう』と私の小さな読者はすぐと言うでしょうが、お子さんたち、違うのです。あなたたちは間違っています。昔々、あるところに1本の棒切れがありました。それは高価なものではありませんでした。それどころか、薪に使われるために束ねられている、ごく普通の棒切れでした。厚みのある、固い木で、冷たい部屋を温めて居心地良くするために、冬に燃やされるものでした」
となっている。この書き出しを、私は大変に気に入っている。王様や有名人などは世の中に沢山いるわけではないのだから、この書き出しは、自分を薪の1本としか感じていない大多数の読者を、すっと主人公に一体化させてしまう。我々の大多数は、社会的に無名の人間として、また、神の前にも誇れるものなど全く持たずに生きて死んで行く。もしも生きることの意味が、人々に貢献して有名人になるこであったり、神のところに誇らかに凱旋できるところにあったりしたのでは、大多数の人間は自分の存在の意味が掴めず、酔生夢死するより仕方がないだろう。ところが、この物語の主人公は、薪にされるような1本の棒切れなのである。
人形作りのジェペツト爺さんがこの木材から作り出したのが、物語の主人公ピノッキオ(Pinocchio)である。この名前を、どのようにしてジェペツト爺さんは考え出したか。「私はこの人形をピノッキオと呼ぼうと思う。この名前は彼を立身出世させるだろう。かっての私の知人に、ピノッキオ一家の者たちがいた。父のピノッキオ、母のピノッキア、子供たちピノッキだ。彼らは皆、運が良かった。1番金持ちになった者は、物乞いで生活していた」とジェペツト爺さんはつぶやく。こんなつぶやきを、本物のストーブが買えなくて、壁紙にストーブの絵が本物らしく描かれ、絵の煙が絵のポットから出ているような部屋の中で聞かされたら、我々は何を感じるだろう。自分より更に下層の人々を見下すことによって自分の優越感を引き出し、そこに生きる意味を見つけるかもしれない貧しい人々でさえも、ジェペツト爺さんよりはましな生活をしているだろう。彼はそれ程に貧しく、世間的には存在の意味さえ認めて貰えない部類の人間なのだ。このような人々の存在の意味は、存在していることだけの中にしか見つけられないだろうが、それが実は全ての人間の本来持つべき意味なのかもしれない。とにかく、そのような環境の中へとピノッキオが存在し始める。
更に、イタリア語の辞書に当たってみると、pinoとは松の木のことで、pinocchioとは松の種子であることが分かる。松は北極圏から赤道近くまで北半球の広い範囲にわたって繁殖する、「岩場であろうと砂場であろうと、不毛の地であろうと増殖してゆき」、「もっとも厳しい寒気にも灼熱の太陽にも耐えうる生命力の強い木」(マイケル・ヴェスコーリ著、豊田治美訳『ケルト・木の占い』、NTT出版、1999年、125貢)である。そして、松の木は、長い間強く燃えるので、薪としては特別に重宝がられていた木材である。自分が何処にでも見られる(珍しくないという意味では)粗末な木材であるにも拘らず、後で述べるように、情熱をかけて自分の実存を生き抜くピノッキオが、既にその名前によって象徴されているのだ。
この物語は恐ろしいほどに孤独な人形の(人間の、と言ってもよい)物語であって、確かに沢山の人間が物語に顔を出してはいるものの、主人公のピノッキオにとって親しい登場人物は、ピノッキオの製作者で父と呼ばれるジェペット、ピノッキオの良心を表わしているらしいコオロギ、その他の動物たち、そして、千年以上も森に住む妖精(La Fata)である。この妖精は、――fataというイタリア語が「ものを作る」という意味のfareに由来することを考えると――、ヨーロッパのキリスト教前の宗教の神々の1人、後述する「運命の女神」と深い関わりを持つと私には思われる。そこでこの小論では、「妖精」という訳と共に「女神」とも訳すことにしたい。ところで、この女神がピノッキオの生涯を暖かく見守っていることは、物語全体を通して我々に感じ取れるのだが、それが明瞭に表現されているところが何箇所かある。それらは、木に吊るされているピノッキオを女神が助ける場面、違った町でピノッキオが空腹で困り切っていた時に、泉より水を汲んできて彼の前を通り、彼を助ける場面、ピノッキオが大きなサメに飲まれそうになった時に、彼に危険を知らせる場面、ピノッキオが木製の人形から本当の人間の子供に生まれ変わる場面である。その内の1箇所だけではあるが、空腹のピノッキオを助けた時に、女神は彼によって「母さん」(la mia mamma)と呼ばれている。女神の髪の色が空色であるという描写が頻繁に出てくることと考え合わせると、ピノッキオが松の種子であるのに対して、女神は松の木ということになる。しかも、濃い緑色の髪の毛ではなく、淡い緑、空の青色に近い髪の色をしていたと書かれているところから察して、ヨーロッパなら何処にでも見られた赤松であったのではないか。つまり、この女神は松の精霊なのであって、ピノッキオが珍奇で貴重な素材でできていないと同様に、この女神も高貴な女神ではないのかもしれない。つまり、『ピノッキオの冒険』は、身分の低い、ありふれた女神と、その息子の物語のだ。
これは、人間社会だったらありふれた存在でしかない、母と子の関係が描かれている物語なのだ。それを、ある人が私に話してくれたように、キリスト教の父なる神と、聖母マリアの子供としてのイエスの物語として読むことは、とても難しいのではないか。確かにジェペット爺さんはやがては人間となるピノッキオを作ったのだから、創造者なる神のように考えられるかもしれない。だが、ジェペット爺さんには神らしい威厳もないし、愛情深い人間として最後までピノッキオを助け出そうとするけれども、結局はピノッキオを助けることができなかった。ピノッキオを助けたのは女神である。どうしてもジェペット爺さんを神の象徴として考えたいなら、彼の象徴する神は正統的キリスト教の神ではなく、二元論的な異端とされたボゴミール派やカタリ派の神であろう。これらの派の源流を尋ねて行けば、我々は初代キリスト教のグノーシス運動に行きつくだろうし、更に遡って、『旧約聖霊』の創造物語に陰を落としている二元論、創造に当たって(神に敵対する)龍と戦い、打ち勝って創造の業を成就する神にまで行ってしまうであろう。教会史における周知の事柄に属するが、ピノッキオ物語の作者が生まれ育った北イタリアは、中世においてカタリ派の栄えた土地であった。従って、この信仰の影響が作者にあったと考えても、少しも不思議ではない。物語の初めの部分で、ジェペット爺さんが大工の友人に、人形を作る材料を買いに来る場面がある。彼が大工の家の戸口にきた時、家の中では大工が、薪の1本がおしゃべりをし出したのでびっくり仰天していた。そして、その木は入ってきたジェツベト爺さんをからかったので、大工がからかったと誤解したジェペット爺さんはおこりだし、2人は取っ組み合いの大喧嘩を始めてしまう。仲直りをして、ジェペツト爺さんはピノッキオを作る材料を買って帰る訳だが、この取っ組み合いは、神とその敵対者との争いを象徴しているのかもしれない。いずれにしろ、このように象徴される神は後のカトリック教会が主張するようになった全知・全能の神とは言い難い。
> TOP
カトリック教会とピノッキオ物語
既に多くの読者がご存知のように、何でも知っていて、何でもできるという意味での神の全知・全能を私は否定している。そのような神が存在していて、しかも、この世にこれほどの罪・不幸・悲惨が存在するならば、もっとも人間らしい名誉ある者たちは、その神に反逆し、その神を殺し、絶望と虚無に生きるのが正しいだろう。何故なら、この世の不条理は、全知・全能なのに、それを防ぎもせず、むしろ不条理を用いて、自分の意志の通りに動かないあらゆる被造物を刑罰するような神は、私には悪魔としか思えないからである。私は中世に異端とされて弾圧されたカタリ派の二元論、神とその神に敵対する悪の勢力との闘争として、現実を理解する立場が正しいと信じている。そのような私にとっては、真の神は愛の存在であって、人間や他の被造物を愛し、彼らと永遠に愛において暮らすために、この世の仕組みをその愛のために利用できる程に知っており、罪や悪や死や、その他の不条理の間を縫って、ご自分の愛の意志を実現できる程に力ある存在なのである。従って、二元論的に考えない場合には、ジェペット爺さんのピノッキオへの深い愛情は、カトリック神学によってイエス・キリストにおいて啓示されたとされている神の愛の象徴となり得るとは思うが、その作り出したピノッキオが余りにも腕白で、(活動し出した特に初めのうちは)自己中心的なので、全くの不完全作品しか作れない神となってしまう。それに対して、二元論的なキリスト教神学であれば、このようなピノッキオの不完全さを、神に敵対する不条理の故に、神もピノッキオを最初から完全には作れなかったからと説明することができるだろう。
ところが、ジェペツト爺さんは、私が信じる二元論的な神の象徴としても、実は適当ではない。彼はピノッキオがそうであったよりも、自分の運命に打ち勝てずに、唯自分の運命に流されてしまっている。確かにジェペット爺さんは、ピノッキオを愛するが故に、ピノッキオを尋ね求めて、遂には海に舟で乗りだし、大きなサメに飲み込まれてしまう程であった。ジェペット爺さんがもしも神の象徴であるならば、神がそのように愛情深いことは、確かに我々を感動させるであろう。そして、ピノッキオによって代表されている我々を、それ程までに愛してくれるこの神に、我々は感謝せざるを得ないし、また、我々はその悲劇的な神に涙し、同情するかもしれない。そして、この神へのこのような同情が、我々の二元論的な神への信仰の持つ重要な1要素であることは、私にもよく分かるけれども、これでは死が神に勝ってしまっている。死の後には復活がなければならないのである。そして、大きなサメからジェペツト爺さんが出てきたのは、つまり、復活したのは、彼自身の信仰や力のお陰ではなく、ピノッキオのお陰なのである。
ところで、ジェペット爺さんが、(また、後にはピノッキオも)大きなサメに飲み込まれたが、また無事にそこから?て来られたというこの話は、『旧約聖書』の「ヨナ書」にあるヨナの物語とよく似ている。後のキリスト者も、ヨナの物語を、イエス・キリストが死に飲み込まれたが、やがて復活したことの予型と見なした。しかし、このことから、いきなりピノッキオ物語がイエス・キリストの死と復活を物語っているという結論を出してはならないように、私は思う。気づいた読者もいるかもしれないが、ローマ・カトリック教会への信仰が社会の土台となっているイタリアに舞台が設定され、イタリア人が書いた物語なのに、この物語には1つの教会の建物も、1人の神父も出てこない。著者コロディが生まれ育った村の近くのフローレンスは、周知のようにキリスト教美術の宝庫である。でも、それへの言及は皆無である。コロディはローマ・カトリック教会を完全に無視している。更に言えば、まるでイタリア社会がカトリック教会とその信仰を土台としている事実を敵視しているかのようである。大きなサメにジェペット爺さんやピノッキオが飲み込まれた事件も、キリスト教とは無関係に、コロディが『旧約聖書』の物語からヒントを得て書いたと考えるべきだろう、と私は思っている。また、最初にピノッキオが女神と出会うきっかけとなった事件、つまり、悪いキツネとネコに襲われたピノッキオが、人形劇場の親方からせっかくジェペット爺さんに渡すようにと貰った金貨を、これらの悪者に渡すまいとして抵抗し、金貨を舌の下に入れて口をどうしても開けなかったので、追剥たちがピノッキオを大きなオークの木に首に縄をかけて吊るして殺そうとした事件は、イエス・キリストの十字架刑の象徴物語のように思われるかもしれない。しかし、私には簡単にそのようには思えないのである。
ピノッキオが吊るされた木は、オークであると書かれている。キリスト教前のヨーロッパで、広い地域に渡って独特の文化をもって栄えたケルト民族は、木を崇拝し妖精信仰を持っていたことで知られているが、ピノッキオ物語は、イタリアに残されたケルト民族のその信仰に養われて生まれたものだ、と私には思える。家の玄関口のドアは、その家に近づく人々がまず出会う場であるが、ゲール語―ゲール人が使ったケルト語―では、duirであった。英語のdoorはこれに由来し、堅実さ・守護・オークの木を意味した。そして、オークの大木はしばしば落雷を受け、無惨な姿を暫く見せはするが、数年どころか百年も生き延びて、その根からやがて子供の木を育てて行くのである。ケルト民族は、ことのほかこのオークを崇拝していた。そして、単に体や生活の守護樹としてオークを大切にしたばかりではなく、人間の霊性を高めるものと見なしていた(Liz & Colin Murray: The Celtic Tree Oracles, St.Martin's Press, 1988, p.36f..)。タロット・カードの大アルカナ12番は「吊るされた男」と言い、逆さまに木から吊るされた男をその図柄としているけれども、この男は古代北欧のゲルマン民族の神話に出てくるオーディン神であると言われている。オーディンが自分自身を吊るしたのはイグドラシルと呼ばれた世界樹、常緑のトネリコの木であるが、この木の上でオーディンは過去・現在・未来に関する知識を獲得した。それは、この木に自分を逆さに吊るすという難行苦行を通してであった。オーディンはこのイニシエーションを通して、死にも打ち勝つような霊性を獲得したと言われている(Freya Aswynn: Leaves of Yggdrasil, Llewellyn Publications, 1994, p.208f..)。ピノッキオは逆さには吊るされなかったし、その吊るされた木も世界樹ではなくオークであったが、しかし、ピノッキオの物語において、この事件が彼の精神的な進歩の第一歩、つまり、女神との出会いに相応しいイニシエーションとなっていることを思うと、この事件はイエス・キリストの十字架を象徴するというよりは、大アルカナ12番をモデルとしているのではないか。
> TOP
森の妖精と観世音菩薩
ところで、森の妖精である女神を、聖母マリアの象徴と見なすのも無理である。ピノッキオ物語では、ジェペット爺さんやピノッキオは、運命に翻弄される存在として描かれており、彼らの運命を左右するのは森の女神である.森とその近所に住む妖精として描写されているこの女神は、ピノッキオが追剥に追われて彼女の家に逃げ込もうとした時に、最初は断わりながらも、既に述べたように、ピノッキオが追剥に捕まって木に吊るされてしまい、息絶え絶えになった時には、彼を助ける。このような仕方で最初に物語に登場した時に、彼女は既に千年以上の年齢を持つと言われていながら、青色の髪を持つ美しい少女として描かれている。更に、ピノッキオが、自分を探してボートで海に出たというジェペツト爺さんを迫って海に飛び込み、流されてある島の海岸に漂着し、食べ物を求めて海岸近くの町に行き、水瓶を持ち運びながら彼の側を通りかかる女神に出会った時には、女神は成人した女性の姿となっていた。一緒に住んで学校に行き、良い子になりなさいという女神の言いつけを守らずに、おもちゃの国に行ってしまい、ロバに変えられてしまったピノッキオが、舞台で芝居をさせられていた時に、観客の中に貴婦人の姿の女神を見つけた。しかし、その舞台で足を挫いたピノッキオは、ロバの皮を欲しがっていた男に買い取られ、その男は皮を剥ぐためにピノッキオに重石をつけて海に投げ込み殺そうとする。幸いなことに海の中で魚たちがロバの皮を剥ぎ取ってくれたので、引き上げた男は役にも立たない1本の棒になってしまったピノッキオを、また海に投げ返してしまった。そのピノッキオを大きなサメが襲って飲み込もうとする。白い岩の上で青い毛のヤギの姿の女神が、ここまで逃げてこいと叫ぶが、遂にピノッキオはサメに飲み込まれてしまう。
ピノッキオと最初に出会った少女の姿をした女神が、森の妖精の性格を一番良く示しているのかもしれない。嫌がるピノッキオに苦い(恐らくは森の植物から作った)薬を飲ませたこと、身の回りに侍らせている動物たち、彼女の命令を実行する動物たちは、犬やウサギや鷹やコオロギなどの、森やその近辺にいるものたちである。彼女は、中世や近代の―カトリックやプロテスタントの―キリスト教会が迫害した、あの魔女の姿をほうふつとさせる。そして、水瓶をもってピノッキオの前に現れた、成人した女性の姿の女神は、恐らくは森の泉から水を汲み取ってきたのだろうから、森の妖精の特徴をこれまた示している。ところが、青い羊毛のヤギとしての女神はどうか。このヤギは、海辺の岩の上に立っている。そうすると、森の女神は、人間を救うために姿や形の違う33の存在に変化することができる観世音菩薩、つまり、変化観音のように振舞うのだろうか。
「立派な若者よ、生ける者たちの中で、仏の身によって救うのがよい者には、観世音菩薩は仏の身をあらわしてかれらのために教えを説き、独りでさとる者の身によって救うのがよい者には、独りでさとる者の身をあらわしてかれらのために教えを説き……」 (紀野一義「漢和対照普門品」、大法輪選書『観音さま入門』、1981年、117頁)
と「観音経」にあるように、観世音菩薩は、殆ど全知・全能と言ってもよい程に、海であろうが山であろうが、森の中であろうが何処でも、その場に最も適した姿形に変化して現れ、慈悲の力で衆生を救う。観世音菩薩であれば、今にも大きなサメに飲み込まれそうになっているピノッキオを、そのサメから救ったのではないか。ところが、森の女神は海上では力を発揮できないのであろうか、ピノッキオがサメに飲み込まれてしまうのを阻止できなかった。このような所に、森の女神が下位に立つ女神であることが歴然と表れている。もっとも、この女神は他の仏や神々と比べて力は劣るかもしれないが、なかなかの知恵者である。それは、海の上では直接には力を振るえない女神が、ピノッキオが木製の人形であることを承知していて、その大きなサメの腹から、同じそのサメに前に飲み込まれていたジェペット爺さんの手を引っ張って、共々に脱出させていることの中に見えている。木製人形は水の上では楽に活動できるのである。小さい女神が頭の良さで、水に浮く木の性質を利用して、偉大な仏や神々と同じ程の働きをしているのだ。
既に拙著『キリスト教と民衆仏教』の中で述べたように、観世音菩薩は、この仏が仏教の中に取り込まれる前には、インドの南端、セイロン島を望むあたりの―舟人たちの目印となった―山の神であり、航海する者たちや漁師たちの守り神であったとする説がある。この点で、観音信仰には聖母マリア信仰の持つ一面との共通性がある。安っぽいマリア・グッズを売っている店で見つけたものだが、私の手元には、天使たちに取り囲まれて空中にたたずみ、下を見下ろしている聖母マリアの姿を印刷したものがある。下では、嵐に出会って今にも沈みそうな舟が描かれ、舟の中の数人が懸命に舟が沈まないように働いている。このように舟人を救う聖母マリア信仰は、まさに観音信仰と同じである。かって日本において、キリシタンの信者たちが聖母マリアに見立てて観世音菩薩像を拝んでいたのは、私にはとても偶然とは思えない。信者たちには本能的に、聖母マリアに見立てられる菩薩像は観世音のそれである、という認識があったのだろう。そして、初めは相似性による見立てであったろうが、やがてはある信者たちの心の中で、両者の同一性が育まれていったとしても、不思議ではない。日本における最初のカトリック宣教師フランシスコ・ザビエルの意図に反することではあったが、自分の信仰を隠すために、キリシタンの信者たちが仏教の諸仏を聖母やイエス・キリストに見立てて拝んでいるうちに、それらの像に慣れ親しみ、それらの仏や菩薩への信仰がそれ自体で立派なものであることを知るようになったとしても、少しも不思議ではない。宣教師たちが持ち込んできた聖母マリアやイエス・キリストや天使たちへの信仰に、それらと矛盾しない形で、仏や菩薩への信仰が付け加えられていったとしても、宗教的には十分に理解できる事柄である。
従って、明治期になって、隠れていたキリシタンの信者たちが姿を現した時に、ローマ・カトリック教会に戻る信者とは別に、祖先たちが信じるようになった(仏教的なものや神道的なものを取り込んだ)土着のキリスト教をどうしても捨てられなくて、ローマ・カトリック教会に戻れない信者たちが現れたとしても、私には当然のことのように思える。そして、土着のキリスト教信仰の出発点は(聖母マリア観音とを1つのものであると感じ出した)マリア観音への礼拝であるが、このようなキリスト教と民衆仏教との融合を成立させた下地が、キリスト教の中に既に存在していた、と私は考えている。排他的なモーセの宗教たる唯一神教がカナンの地に進入してきた時に、それは宗教的に無地の場所に入り込んできた訳ではなかった。カナンには、アニミズム的な種々の信仰が既に存在していた。アニミズムは、(山や森や川などがそれ自体神々であるという、今日の表現を使えば)汎神論と言われるものではない。それは、山や川や森の木々が、小さな神々によって住まわれており、その神々によって支配され、養われているとの信仰である。やがて、それら沢山の神々の中でも、上下関係が成立するようになる。例えば、初めは特定の地域だけで山の神として信仰されていた観世音菩薩が、阿弥陀仏の国、西方極楽浄土を(阿弥陀仏の後、)受け継ぐ仏として尊崇されるに至った事実に見られるように、アニミズム信仰は、それ自体を変えて流動しながら、民衆の心の中に深く入り込んで行く。マリア信仰も、地中海地域の広い範囲でキリスト教前から信じられていた(アニミズムに由来する)大地母神が、キリスト教の装いを身に付けて登場したものだ、とよく言われる。イスラエル民族がカナンの地に進入してきた時に、彼らが持ち込んできた唯一神信仰は、例えばバールと呼ばれていたアニミズムの偉大な神を信じていた土着の信仰と、衝突せざるを得なかった。この衝突は、預言者たちを巻き込んで、熾烈な抗争を繰り返したものだが、我々は衝突の局面だけに目を向けてはならないだろう。衝突と抗争の繰り返しの深みで、アニミズムと唯一神信仰との融合が進行していた事実を、我々は見逃すことができない。それがユダヤ教の中に成長してきた天使信仰であろう、と私は考えている。つまり、唯一神ヤーウエの下位に立つ天使たちという形で、アニミズムの神々がユダヤ教の中に取り入れられていったのである。
それ故に、隠れキリシタンたちが、仏や菩薩を(天使のように)唯一神の下位に立つ存在として受け入れる下地が、既に(ユダヤ教から天使信仰を受け継いだ)キリスト教の中に存在した、と言える。(明治期になっても、ローマ・カトリック教会に戻らなかった)このような日本に土着したキリスト教であれば、森の妖精、女神をも、(観音の下位にありつつも)幾分は観音のように変化のできる女神として、しかし、飽くまでも(個人の住宅の庭に祀られるイナリ神や、小さな池の辺に祀られる弁財天の小さな社のように)小さいが故に、きわめて身近な女神として受け入れることができるだろうと、私は考えている。私がイタリアの作家の物語を、このように取り上げているのは、日本の土着の神々や仏を受け入れる可能性を、果たして日本に入ってきたキリスト教が持っているかどうかを、私に考えさせるからである.少なくともこの物語では、コロディがローマ・カトリック教会に冷淡であるかのように見えるのも、また私に、キリスト教の鋭く偉大な愛の神への信仰なしで、小さな(森の妖精のような)神への信仰だけで、本当に我々は信仰的に豊かに生きられるのか、との問いを投げかけてくれるが故に、貴重な事柄なのである。
> TOP
神の偉大さとは
神々や仏の世界は、上に述べたように、偉大な神が小さい神々を支配するところなのであろうか。このような事柄を考える場合には、神を偉大にするものは何かを考えることから始めなければならないであろう。
力を使って偉大な神が他の神々を支配する、上から下への統治を考えることもできるけれども、しかし、逆に下から上に行く道も考えられるのではないか。一群の神々が自分たちの尊敬できる神を選び、更にそのように各群から選ばれた神々が、自分たちの中から尊敬できる神を選ぶのである。このようにして、最後に選ばれた神が義務として全てを司って行く。そして、尊敬の基準は愛の深さであるとしたら、どうだろうか。力が必要な環境の存在を否定しないが、しかし、それよりも愛を優先するのが神々の社会であり、また、それに倣わねばならない人間や動物、自然の世界なのである。私にとっては、イエス・キリストの父なる神は、まさにそのような意味における至高者である。そして、この至高者は、愛に反する行動をとる不条理世界と戦わねばならないのである。このように考えるならば、アニミズムをキリスト教の世界から追い出す必要がない。
> TOP
キリスト教はアニミズムとどのように関わるべきか
また、何故にアニミズムの世界をキリスト教信仰の世界から追い出したくないかというと、それを追い出すことで、キリスト教信仰が自然と無縁なもの、この世界から全く超越したものとなってしまうからである。全被造物の頭として神によって創られた人間は、この自然世界を人間の利益のためだけに利用して構わないという、自然破壊に繋がるキリスト教的考えを生み出してきたのは、まさにアニミズム的なものを悉く否定した西欧のキリスト教であった。我々はもう一度、アニミズムを取り入れて天使信仰を生み出してくれた、ユダヤ教や原始キリスト教の知恵に戻らねばならない。
また、我々は、ピノッキオの世界に見られるような、キリスト教的な愛の至高者の否定も避けるべきではないか。世界における悪の力、不条理は、小さな神々の独りが戦って勝てるような脆弱なものではない。アニミズムも、それにはとうの昔から気づいていて、独りの神の力を超えた法則のようなものを、神といえどもそれには従わざるを得ないものを信じてはいた。例えばそれは、完全ではないが死という不条理に対してのある程度の勝利を与えてくれる輪廻転生であり、死後の命の存在であった。この信仰はピノッキオ物語にも顔を出している。初めの部分で、自分の悪いいたずらをコオロギに注意されたピノッキオが、そのコオロギを木槌を投げて殺してしまう場面があるが、そのコオロギは死んだにも拘らず、−ピノッキオが悪いネコとキツネに騙されているとも知らずに、人形芝居小屋の棟梁から貰った金貨を増やそうと躍起になっていた時に、−生きている霊的存在として、またピノッキオを諫めるのである。私は、このような輪廻転生や死後の命のアニミズム的信仰が、永遠に渡る神との愛の交わりに至る道程に過ぎないと思っているが故に、不完全ではあるが、道程として考えればその信仰を否定する理由は全くないと考えている。拙著『神と希望』(日本キリスト教団出版局、1980年)の中で詳しく述べたように、輪廻転生や死後の命への信仰は、『新約聖書』の中でも否定されてはいない。
だが、永遠に渡る愛の神との交わりは、アニミズムの輪廻転生や死後の命への借仰を超えている。つまり、輪廻転生や死後の命を与える自然の法則が究極のものではなく、それらの法則を内に含んで、(否定しないで)それらの土台となっている、永遠の愛の意志こそが究極のものなのである。人間にとって究極的なものは、キリスト教の説く−イエス・キリストにおいて啓示された−神への信仰なのである。十字架の贖罪、罪の赦し、永遠の命などは、人間の永遠の次元に属する事柄であり、キリスト教はまさにこの次元において我々に信仰を喚起し、死をも克服させる生の土台を提供してくれる。しかし、この世に生きる限り、人間はこの永遠の次元だけで生きてはいない。物質的な恵み、自然の恩恵なしでは日々を生きられない。その時間の次元こそが、アニミズムの神々の領域なのである。『旧・新約聖書』が天使信仰を受け入れていたのは、まさにこれらの小さな神々に自然の領域での(人間に対する)恵みを伝達する役割を期待していたからである。いわゆるご利益信仰は、キリスト教が完全に捨て去ってよいものではない。
勿論、誰もが森の近くに住んでいる訳ではないから、特に現代の都会人には、森の妖精を自分の守り神とすることは、実在感を欠き、殆ど不可能でもあろう。しかし、誰にとっても、自然の材料−木材や石や土など−から作られたもの(例えば、コケシ、マトリヨーシュカ、紙製の人形や動物、焼物、彫刻作品など)で、自分の生活に欠かせないもの、また、愛するものがあるだろうから、ピノッキオにとっての森の妖精に当たるものは、我々の生活の中に一杯ある。それらを通して、キリスト教の愛の神は、自然の恵みを我々に伝達して下さると信じれば、アニミズムの神々がキリスト教信仰の中でそれらの場所を得ていることになる。
しかし、我々が忘れてはならないことは、コロディのカトリック教会への無視にも拘わらず、キリスト教の愛の神―人間の罪をあがない、また、赦す神―への信仰がその土台となっていないアニミズムの神々への信仰が(人間を心底から生かす点で)不十分であるからこそ、私などが懸命に両者の共存、否、キリスト教信仰の中でアニミズムを生かそうとの努力をしているという事実である。アニミズムの神々への信仰は、基本的にはご利益信仰であり、自分の(いろいろの意味での)生の充実追求である。それは最後のところで、隣人をも自分のために犠牲にしてしまう。これでは愛の共同体が、人間同士の間にも、人間と動物、人間と自然環境との間にも、生まれる筈がない。隣人のために自分の命さえも投げ出すキリスト教的愛がまずあってこそ、自己の利益追求は許される。アガペー(ひたむきな他者への愛)とエロス(自己への愛)をどのように関係させながら生きるかについては、残念ながら紙数の都合上、ここでは述べられないが、拙著『実存論的神学と倫理』(創文社、1970年)などを参照して下さると有り難い。アガペーだけを良いとしてエロスを弾圧すれば、そこにあるものは非人間的な禁欲主義だろうし、エロスだけを良いとしてアガペーを排除すれば、そこに出現するのは弱肉強食の恐ろしい世界であろう。
> TOP
人形療法
 ウォルト・ディズニー(Walt Disney)の名作童話館に入っている絵本『ピノキオ』を、私も愛する者の1人だが、この本では森の妖精が星の女神に変えられている。「星に願いを」という歌とともに、子供たちの間では定着してしまっているようにみえるが、森の妖精を星の女神に変えてしまった人物は、ディズニーの前にもいた。二葉書店という
ウォルト・ディズニー(Walt Disney)の名作童話館に入っている絵本『ピノキオ』を、私も愛する者の1人だが、この本では森の妖精が星の女神に変えられている。「星に願いを」という歌とともに、子供たちの間では定着してしまっているようにみえるが、森の妖精を星の女神に変えてしまった人物は、ディズニーの前にもいた。二葉書店という  ところが、橋本明夫訳の『ピノチオの冒険』を昭和21年(1946年)に5円で出版しているが、そこに出てくる女神は「女神」と呼ばれ、星を前面に象ったヘアバンドを付けている。しかし、この変化はあまり歓迎できないのではないか。同じアニミズムに立つものではあるが、女神が近くにある森の妖精であってこそ、我々一人一人の運命を身近に司ってくれる存在を我々が持ち得るのである。その女神が、地球の遥か彼方に住む―たとえその女神が、我々のところを時には訪れてくれるとしても―星であっては、(北極星を信じる)妙見信仰と同じように、その女神は崇高な存在であるが故に、崇拝の対象としてはよいだろうが、身近な世話まではなかなかお願いできない。
ところが、橋本明夫訳の『ピノチオの冒険』を昭和21年(1946年)に5円で出版しているが、そこに出てくる女神は「女神」と呼ばれ、星を前面に象ったヘアバンドを付けている。しかし、この変化はあまり歓迎できないのではないか。同じアニミズムに立つものではあるが、女神が近くにある森の妖精であってこそ、我々一人一人の運命を身近に司ってくれる存在を我々が持ち得るのである。その女神が、地球の遥か彼方に住む―たとえその女神が、我々のところを時には訪れてくれるとしても―星であっては、(北極星を信じる)妙見信仰と同じように、その女神は崇高な存在であるが故に、崇拝の対象としてはよいだろうが、身近な世話まではなかなかお願いできない。 ある知人の親しいご友人で、私も2、3度おつき合いをしたことのある方が死の床にあると聞き、私もご一緒にお見舞いすることとなった。死にゆく方にどのようなお別れができるのか、しかもそれ程親しいおつき合いをしたこともなく、キリスト者でもない方に、どのようにして私は慰めとなるお別れができるのか、と随分考え込んだ末に、私はふと目に留まった机の上の小さなマトリョーシュカ、ロシヤ人形を持って行くことにした。病院での差し障りのない会話の後で・私はそのマトリョーシュカを取り出し、次のような話をしてお渡しした。「この人形は神様ではないから、小さいことしか私たちのためにしてくれることができません。しかし、この人形にご自分の息をふーと吹きかけて下さい。何時でもその人形と話したくなった時は、そのようにして下さい。そして、何でも話して下さい。また、小さな願いなら、その人形は一生懸命にあなたのために働いて実現してくれるでしょう」と。『旧約聖書』の「創世記」に、神が人間を創られた後、ご自分の息を吹き込まれ、人間は生きるようになった、とあるが、今日でも、アメリカの先住民のある者たちは、自分を守ってくれる動物などを小さな貴石などに刻み、それに息を吹きかけては願い事をし、また、お守りとして持ち歩く。これはアニミズムの宗教性の一端を示している。息を吹きかけるのは、その石などに住み着いてくれた小さな神や霊と自分との交わりを作り、また、深めるためであるが、そのような宗教的習俗には、1つの石が割られると、1つ1つの割られた石に前と同じ神なり霊なりが宿るという、アニミズム的信仰が土台となっている。人間が死んで行く時には、誰にも言えない、恥ずかしくて―そんなことは実はないのだが―至高者にも言えない、怒りや不満や悲しみがあるものだが、それを聞いて慰めてくれる小さな神や友人としての霊が身近にいてくれる方がよいに決まっている。疲れた病める精神の持ち主に対する人形療法と、私はこれを呼んでいる。
私が差し上げたマトリョーシュカは、その方の棺の中に入れられたとのご報告をいただき、それは私にはとても嬉しいことであった。
> TOP
運命の女神とゲマトリア
ところで、ピノッキオ物語では、森の妖精がLa Fataと呼ばれていることを、私は前に述べた。この意味はfataleという同じ語源からきた言葉が示しているように、作られてしまっていて、それには反抗できないようなもの、つまり、我々の運命を作る存在、女神を指し示す。森の妖精は「運命の女神」なのである。周知のように、ヘブライ語の1字1字を数字に直して、ある言葉の隠された意味を探るゲマトリアと呼ばれるものがあるが、「ヨハネの黙示録」などにもこの解釈法が採用されていることもよく知られている。原始キリスト教徒が、ユダヤ教の中のこの解釈法に影響されたのである。そして、この解釈法は、実はピタゴラスもその信奉者の一人であった、ヨーロッパの古代以来の数に対する信仰に由来する。現実のあらゆるものには数が付着しており、それらの数がそれらのものの本質を顕示するという信仰なのであるが、この信仰がユダヤ教の中にゲマトリアという解釈法を生み出したのであった。「運命の女神」は3という数字と深い関わりを持っている。ピノッキオ物語では、この関係が隠されてしまっているが、それは恐らく、著者のカトリック教会への反抗にも拘らず、この物語に登場する女神が、『新約』に描かれている愛の世界に影響されて、元来は不条理な仕方で人間の運命を決定して行く「運命の女神」が、愛の決定論、あるいは、愛の運命論―私はこれを拙著『実存輪的神学』(近く松鶴亭(出版部)により復刊される)などで、宿命論と呼んだが―とでも言うべきもので、人間を見守って行く存在に変化してしまったからであろう。
何年か前のことだが、用事で時々行くことのあったある町で、1軒の古書店のショウウィンドウに『運命の女神』という表題の本が飾られていた。その道を通る度に、どうしようかと迷っていたが、ある日とうとう中に入ってその本を見せて貰い、買ってきてしまった。この本は、私に森から来る3人の運命の女神を教えてくれる書物となった。まるでその本自体が、私を運命的に招いてくれて、自らを私に買わせたような気がしてならない(このような運命としか言いようのない書物との出会いを、私は何回も経験している)。丁度その頃の私は、人間にとって運命論が、例えばカルヴァン主義の予定論やイスラム教徒の運命信仰が、人々に慰めと精神的な力を与え得る事実を、またまた考え込んでいた。この問題は、十代の頃から、私の心を離れない問題なのであるが、神学者として実存論的な思考をするようになってからは、解決を迫る特に熾烈な問題となっていた。実存論的思考からすれば、人間の主体性を強調することに重点が置かれてくるのは当然であり、このような人間の自由の強調は、神が人間を支配するという信仰の局面を縮めて行く。私の向こう側に立ち、私を支配する神の働く領域はどんどん少なくなり、人間の決断が、行為がその領域を拡大して行く。それが極まれば、神を抹殺する―ニーチェやサルトルに見られるような―無神論、神殺しとなる。あるいは、神を私の向こう側に立つ人格的存在とすることを締めて、神をこちら側に持ってきて、私の存在を支えてくれる土台のように考えてしまい、私の深い本質が、神という私の土台に根を下ろしている、と考える―ハイデッガーのような存在論的な神秘哲学に逃げることとなる。私は、このいずれも自分の立場にしたくないのである。キリスト教信仰は、私にとっては、人格的な神の支配―ただし、愛の支配であって、力づくの支配ではないが―と、人間の極限までの主体性との両方が生かされるものなのである。
『運命の女神』という、私が買い求めてきた書物は、正確にはブレードニヒ著・竹原威滋訳『運命の女神―その説話と民間信仰』(白水社、1989年。原著はRolf Wilhelm Brednich: Volkserzähulungen und Volksglaube von den Schicksalesfrauen, Helsinki, 1964)である。著者ブレードニヒは、運命の女神に関する説話を集め、それらに注釈を付け加えて、それが具体的にどのような信仰であり、時代を経るにつれてどのように変化して行ったかを検証しているのであるが、前に述べた3という数字がこの書物でも重要視されている。3という数字に関しては、この数字を見る度に、イグナチウス・ロヨラが涙を流したというような伝説が残されているが、これは勿論、3がロヨラに三位一体を意味する数字であったからだ。同じように、日本仏教での阿弥陀三尊、ヒンズー教の創造神ブラフマ・破壊神シバ・維持神ヴィシュヌ、エジプトのイシス・オシリス・ホルスの3神などが、3という数字の意味を豊かにしてきたと言えるだろう。更に、ギリシャの3神モイラや、ヨーロッパの前キリスト教時代に民衆の間に深く根を下ろしていたノルヌという3女神がある。以上のような3でまとまっている神々や仏たちが、3という数字の意味内容を既に述べたように豊かにしてきた訳だが、これら3女神こそがブレードニヒの著書の主題であり、また、ピノッキオ物語に登場する森の妖精の元来の姿なのである。
運命の女神に関して3は、女神が運命の糸を紡ぐ、人間1人1人にそれを割り当てる、割り当てた糸を断つ、という3局面を意味している(3に関しては、ジョン・キング著、好田順治訳『数秘術−数の神秘と魅惑』青土社、1998年の中の3に関する言及、特に99-100頁を参照されたい)。その人の運命がどのようなものになるかを紡ぐのも女神であり、それをその人に結びつけ、割り当てるのも女神であり、その糸を切断しその人を死に追いやるのも女神である。これは運命論であり、人間にはこの運命を変える力は全くない。ただその運命に服従するだけである。
ある時、イタリア系アメリカ人で大学教授である知人に、ピノッキオ物語に出てくる「運命の女神」が、今は私の興味の対象であると話したことがあった。その時に、彼は幼い頃、運命の女神のことを聞くと、恐くて仕方がなかったという話をしてくれた。彼が生まれたのはアメリカ合衆国であったのだが、イタリアから移民してきた父親や親戚の人々から「運命の女神」について聞かされたとのことであった。つまり、彼の前の世代のイタリアでも、まだこの女神への信仰がその影響の残りを投げかけていたのだ。
ブレードニヒ『運命の女神』によると、文献的に残っているこの女神への信仰は、シュメール文明における「ギルガメシュ叙事詩」にまで遡れるとのことである。ここでの運命の女神は、冥界の女神マメトウンである。ギルガメシュの生涯は、その誕生前から神々によって決定されていた。少しく詳細に、この物語の筋書きをここで追ってみよう。占い師たちが王に、娘婿が王国を奪い取ることになると予言した。そこで、王は娘を塔に閉じ込め、監視させていたが、娘は塔内で密かに父なし子を生んだ。神々の協力のお陰で、その子は立派な体と美しさと英雄の心を与えられた。そして、その子は鷲によって攫われ、ある庭師に育てられたが、これが後に王国を奪い取ったギルガメシュであった。既にこの叙事詩の中に、民間に伝わる数多くの運命説話における重要な3つの観念が明瞭に見られる、とブレードニヒは言う。それらは、(1)予言、(2)予言された運命の成就を妨げる試み、(3)それらの試みにも拘らず、予言は成就してしまう。
この運命信仰は、古代エジプトでもほぼ同じような形で見られる。ここでは神々の方が運命の上に立っており、運命は人間などに神々が与えるものとなっているが、出生の日に、生まれたその人物の運命は死亡の時刻に至るまでも決定されているのである。ギリシャの神話や英雄伝説でも同じように、誕生時にその人物の運命が宣告される。ホメロスの作品の中でも運命の女神モイラが、例えばアキレウスの誕生時に、彼の一生の運命を紡ぎ出した、とある。他の英雄たちについても、同じことが言える。
ブレードニヒが挙げているキプロスの民間説話資料は、後代に渡る運命の女神信仰の典型を伝えていて、重要なものと判断できるが故に、ここに引用しておこう(27頁)。
ある女が1人の男の子を生む。その子が生まれて7日後に、3人の運命の女神、モイラたちがやって来る。1番目の女神は、この子は美男になると予言する。2番目の女神は、この歌い手になると予言する。ところが3番目の女神は、火の中の薪が燃えつきればすぐに死ぬと運命を定める。母親は火を消し、薪を長持に隠す。その子は美男の歌い手になり、王女と結婚する。しかし彼が伯父を殺したとき、母親は復讐心から薪を燃やしてしまい、青年は死ぬ。
人間の寿命を臨終の時に消えてしまう火と見る見方は、古代から現在に至るまで続いている観念だが、引用されたこの説話には、子供の誕生の数日後にモイラたちが訪づれ、その子の生涯を予言し、その予言によってその子の生命が拘束されるという、今日に至るまで特に東ヨーロッパ圏に広く行き渡っている運命の女神信仰がよく表わされている。そして―これも広く行き渡っているのだが―3人の女神が訪れてきて、予言の最後の言葉は最年長の女神によってなされ、幼子の生涯が何時、どのような仕方で終わるかが宣言されるのである。ここに数字3が、またも大きな意味を持っている。
ピノッキオ物語においては、森の妖精である「運命の女神」(La Fata)は1人で行動する、どこか孤独な雰囲気を漂わせている女神として登場する。3人1組で活動した古い運命の女神たちとは、どこか違っている。キリスト教がヨーロッバに広く深く受け入れられるに至った後では、ブレードニヒが言うように、この決定論的な運命信仰に、微かではあるが修正が加えられた。つまり、神やキリストに祈ることによって、予言された死を回避できるとの信仰が、この運命の女神信仰に微妙な陰を落とすようになった。そして―これは私の勝手な意見なのだが―キリスト教信仰が持つ強烈な主体性、つまり、神を信じることは全く孤独な魂の孤独な決断であるという個人性の強調が、人間だけではなく運命の女神までも、個人として活躍させるに至ったのではないだろうか。既に述べたように、この点でもピノッキオ物語は、作者のカトリック信仰の無視にも拘らず、キリスト教信仰の影響を受けてしまっているのではないか。
しかし、いずれにしろ、ピノッキオ物語の1つの極が、古代より人間の心を支配してきた運命論の受容であることは疑いの余地がない。アニミズムの妖精信仰、ピノッキオの運命を司る、優しい愛の女神が身近かにいるとの信仰が、遠くにいる至高の神では頼めないような事柄さえも聞いてもらえる(小さな)神がいるとの信仰が、この物語の大きな魅力なのである。
ピノッキオ物語に見られる運命論は、人々の心に穏やかさと安心感を与えてくれる。自分の運命を司ってくれる小さな神々が存在せずに、ただ偉大な至高の神だけしか存在しない場合には、人間はこの広大な宇宙空間の中で、また、尽きないとしか言いようのない時間の流れの中で、その至高の神から命じられた自分の使命を果たさねばならないとの焦りで苦悶する。遂には何も果たせない自分に絶望し、自分の存在の意味が分からなくなってしまいがちである。ところが、小さな神々が与えてくれる小さな運命、しかも、自分がどれ程に逆らっても殆ど変えることができない運命を知るようになると、至高神のために何もできなくても、これで良いのだ、との安心感と安らぎが生まれてくる。これは信仰のミニマリズム、日常の些細な事柄の尊重と言ってもよいものかもしれない。
勿論、私はここで、キリスト教を信じる者は皆、小さな神々を信じなければならない、と言うつもりはない。そのようなことを言うならば、それは信仰の中に1つの律法主義を持ち込むことになってしまうだろう。小さな神々を信じること、アニミズムとキリスト教とを習合させることは、1人1人の信者の自由であり、信者の義務ではない。もしも我々が、ピノッキオ物語における森の妖精や、日本の民衆宗教のイナリ神やその他の小さな神々に相当する身近かな神的存在を、自分の信仰の中で実感できるならば、それはそれで良いのだ、と私は考えている。例えば、死んで3日目に甦り、今は天において父なる神の右に座しておられる霊なるキリストか、あるいは、聖書が、その信者にとって今、自然の世界の中で働いておられ、自然の中で我々と出会い、また、日常の我々の自然に依存した生活においてご利益を与えて下さる存在として、真実信じられ実感されているなら、それはそれで良いのだ。つまり、その時には、アニミズム的な信仰が、(教会史上ではアニミズムとは異なり、自然からの超越をむしろ特徴としてきた)三位一体の第二位格(キリスト)や第三位格(聖霊)の中に侵入してしまっている。教会史上の三位一体論とは異なり、パウロの信仰では、既に述べたように、天上にいるキリストが、日常自然の中に生きている我々のところまで霊として降りて来て下さるのだから、近代の科学的合理主義に立つ、アニミズム否定の教会の信仰とは違う。近代合理主義的信仰とパウロ的信仰のうち、どちらを自分の信仰生活の実体として選ぶかは、確かにその人物の自由な決断の問題だが、しかしその人が生まれ育った地域の宗教状況が大きく作用するだろう、と私は考えている。
> TOP
ピノッキオの主体性
さて、ピノッキオ物語には、上に述べた運命論だけではなく、もう1つの極がある。それは強烈な主体性であり、孤独な、しかも自分の良心に対して責任を持つ行動の強調である。嘘をつくとピノッキオの鼻が長く伸びてしまうという滑稽な描写は、この嘘が、個々の嘘と言うよりは、ピノッキオの全存在が、その頃はまだ森の妖精に対して心を開いておらず、彼女に対して嘘の塊でしかなかったという実存的事情を指しているのだろう。
主体性の強調が、例えばジャンルイジ・トツカフォンド(Gianluigi Toccafondo)の描いた『ある棒人形の話―ピノッキオの冒険』という画集において見られる。ところが、ここでは、主体性の強調が森の女神との関係の中で語られてはいない。主体性は、私にとっては至高の神や、小さい神々や、隣人との関係の中で実現するものなのだが、この画集でも、確かに森の妖精は現れてはいる.しかし、女神はこの画集では、ピノッキオの運命を左右する存在ではなく、1人の少女としてだけ現れてくる.そして、元来のピノッキオ物語では、森の妖精は1度死んで墓まで作られたのに、また「働き蜂の島」で水瓶を持つ女性としてピノッキオの前に現れてきており、復活や転生を繰りかえし得る、変化の存在であった。そのような力は、この画集の中では、森の妖精に帰せられていない。1度死んでしまった後は、彼女は画集から全く姿を消している。ピノッキオの運命を司る森の妖精の極は、このように最小限の描写しかされていないのに、ピノッキオの主体性がそれに代わって強調されている。ロバにされてしまったピノッキオが遂に逃げ出す場面のところで、トツカフォンドは「僕は、逃げる。僕を助けられるのは、僕だけだ。僕を助けてくれるのは、僕の脚だけだ。僕の手だ。僕の頭だ」と注釈を付け加えているが、孤独なピノッキオの姿が見事に表出されている。
更に、トッカフォンドは、私の言う不条理の世界を、この画集の中で描いている。木の手、木の脚ばかりか、ピノッキオは木の脳味噌しか持っていないので、最初からピノッキオは悪がどのようなものであるかも知らない。それも彼が生きて行くうちに、学ばねばならないものなのである。従って、子供らしい怒りに駆られて、彼がコオロギを殺してしまっても、前もってそれが悪であるとはピノッキオは思っていなかった。このようにして、彼は悪がどのようなものであるかを経験によって徐々に知って行くが、彼が人々や動物たちに迷惑をかけるのも、子供らしい無知から出たものだ。金貨を何倍にも増やそうという誘惑にかかってしまったのも、ジェペツト爺さんへの愛情からであったし、おもちゃの国に行き、ロバに変えられてしまったのも、子供らしい好奇心からであった。彼が女神やジエェット爺さんなどにかける迷惑は、大部分がこのようなものであったにも拘らず、どうしてピノッキオはあれ程の苦しみや悲しみを味わわねばならなかったのか。ピノッキオは道徳的な悪、神への反逆を犯したというよりは、大人になって行く過程で彼は多くの不条理的体験を強いられたに過ぎない。ピノッキオ物語は、不条理の間を縫って展開される、悪戦苦闘の子供の物語なのだ。
自分の絵についての注釈めいた言葉の中で展開されるトッカフォンドのこのような思想は、私の共感を誘い出す部分が多い。コロディはピノッキオを、そのような不条理の中で苦闘する子供として描いている、と私も思う。キツネとオオカミに騙されたことを裁判所に訴えたところ、不条理にもピノッキオの方が牢屋に入れられてしまい、4ケ月後にやっと開放されたピノッキオが、森の女神のところに帰ろうとして急いでいると、道には大蛇がいる。ピノッキオは大蛇が道からどいてくれるのを何時間も待っていたのだが、一向にどいてくれない。そこでピノッキオは大蛇に頼んで通ろうとするが、それができない。やがて、(恐らく)居眠り(の振り)をし出した大蛇の上を乗り越えようとしたピノッキオは、大蛇によってひっくり返されて、泥んこの中に逆さまに、脚だけ出してバタバタする羽目になってしまう。すると大蛇が大笑いして、その大笑いの動作で突然死んでしまう。ほうぼうの体で去っていったピノッキオは今度は、(鶏を盗みに来るイタチを捕まえようとして、農夫が作った)罠にかかってしまう。まさにピノッキオには全く責任のない不条理の連続だが、これらの物語の中で大蛇の物語は私には特に面白い。『旧約聖書』でもそうだが、オリエント神話などでは、大蛇(や龍)は神に敵対する勢力として出現する。神はそれらと闘いながら創造の業をなさっている、と述べられている。ピノッキオ物語の大蛇も、女神への道を阻む不条理なのだろうが、このような(大蛇で表現されている)不条理には、笑いで対するより仕方がないのだ。不条理を滑稽なものと見なして、笑い飛ばすことが、唯一の対処方なのである。
ところで、女神の愛や導きは、目に見えるものではない。従って、女神を信じないことも容易である。この物語から女神を取り去ってしまえば、残るものは孤独と寂しさと、その中で苦闘するピノッキオだけだ。これが―すなわち、女神の導きを無視した、あるいは、女神を信じない―トッカフォンドの描いたピノッキオの冒険であった。この画家が、「信じる」という言葉を使っていても、それは自己の力だけで生きて行くことの可能性を信じるだけである。女神のピノッキオに対する導きを絶対化する運命論だけが主張されると、ピノッキオの動きは何の意味もなくなるけれども、逆に、トツカフォンドのように女神の働きを取り去ってしまうと、自力万能の実存主義だけが残ってしまう。空想的には、人間は自力で生や死、理由もなく与えられる苦しみや不幸、つまり不条理と闘って勝利を収めることも可能だろうが、実はそれは―自分や他人にこれでもか、これでもかと理由もなく襲いかかっててくる―人生の悲しみや苦しみに対する鈍感さを表わしているにすぎないだろう。人間が実存的に自力で勝てる程に、不条理は容易い相手ではない。このような態度を続けていれば、人間はやがてはニヒリズムに根底から蝕まれて、生きながらに絶望で死んでしまっているだろう。だが、神や、女神のような神の下位に立つ存在を信じたからといって、何もしないですむものではない。ピノッキオのように全力を尽くして生きない訳には行かないだろう。
否、女神の導きを信じれば信じる程に、物語の終わりに近づいたピノッキオは、その導きへの感謝から、また、女神への愛情の故に、全力を振り絞って正しく生きようとした。ピノッキオ物語を正しく読んで行くと、どうしても神々の運命論と、ピノッキオの主体的な、激しい動きが、全く矛盾しないで両立している。このような事情を知れば知るほどに、私には神々による運命論と、人間の主体的な激しさとが共に必要なのだ、との思いが深まる。かって私は、この事情を「宿命」という言葉で表現したが、今もそのようにしたいと考えている。実存論的神学は実存主義哲学ではなく、神学であり、主体的に生きる実存の自由の角度から、神や神々を考えて行こうとするものなのである。
神や神々による我々の運命の創造(つまり、運命論)と人間の主体性との関係は、どうも合理的な説明を拒否しているようである。私にもこれは説明できない。巻物の譬えで満足するより仕方がないのかもしれない。巻物を拡げて、初めから徐々に絵なり文章なりを見たり読んだりして行くことが、激しい主体的な人生を送らねばならない、我々の時間に支配された姿の譬えであり、それが我々が存在し始める前から既に完結したもの―既に棒状に巻かれたもの―として神や神々の手中にあることが運命論の譬えなのである。
> TOP
キリストの十字架は生きることの否定ではない
ところで、キリスト教が、例えば日本に既に土着してしまった諸宗教と(前に述べたような形で)習合することは、(キリスト教の本質から見ると)余計な事柄であって、対話をそれらの宗教と持つために仕方なく行なう事柄、であってはならない。そのように仕方なくなされる習合は、無理があるし、両方にとって本質的に有り難いものではないだろう。幸い、キリスト教には、習合を本質的に喜ぶ局面がある、と私は考えている。その神学的な根拠は、キリスト教の神が愛だからである。愛には、多数の存在を巻き込みたいとの欲望がある。単独で行なった方が合理的で、早く出来上がることが分かっているような事柄であっても、愛にはその合理性や迅速性をある程度捨てても、多数の存在の協力を要請するようなところがある。つまり、存在の目的は、物事の迅速な達成や、いきなりの豊富さには、究極的にはない。愛の交わりを作り上げることこそが、存在の究極的な目的なのである。人間(や他の動物たち)の存在の意味は、何かを多量に行なうという業績にはなく、最後の処は、何も出来上がらなくても、互いに愛を深く味わえば味わう程、それで善いとするところにある。
例えば、ここにピノッキオと同じように優しい運命の女神を愛しながら、森の近くに住む日本人がいるとする。彼あるいは彼女は、仮にキリスト教徒となった時に、いつも自分の運命の女神への信仰と、キリストの父なる神への信仰とを、心の中で切り離した上で、また、接着しているのだろうか。すなわち、キリスト教信仰の下に、(本当はなくてもよいのだが、自分の過去の信仰を捨てる訳にも行かないので)無理矢理にぶらさげている運命の女神への信仰では、私の神学から見ると困るのである。キリスト教の神は、ご自分1人で十分にその彼なり彼女なりを幸福にすることができるわけだが、お1人でそれをなされるよりも、できる限り多数の存在を巻き込まれることを喜ばれるのである。何故なら、それがキリスト教の説く愛の本質だからである。このようにして、信徒たちは、本当の愛がどういうものかを学ぶのである。
もう1つ例を挙げておこう。日本の民衆宗教の中に有名な七福神信仰があるが、その中に通常含まれる神仏に、寿老人や福禄寿が存在する。この地上の生の長寿・延命・健康などを、人々はこれらの神仏に祈る。ある種のキリスト教徒は、このような祈りは、人生の真っ盛りに十字架にかかって死んでいったキリストを信じる者のなすことではない、と言いかねないだろう。まるで早死にを奨励するような、このようなキリスト教神学に支えられていたのでは、キリスト教は日本では将来がないだろう、と私は考えてしまう。確かに人生には時に、人々のために生命を抛たねばならない時期があるだろう。しかし、実際には、人に奉仕をすることができる日々は、願ってもなかなか存在するものではないし、自分の生命を抛ってもよいと想うような現実は、我々にはそう矢鱒に与えられるものではない。我々にそのような現実が与えられた時には、キリストに倣って我々も喜んで命を抛つべきであろう。だが、そうでない現実のために命を抛つなら、それは無駄死にだし、本来はただの自殺に過ぎないのに、その自殺に、無理矢理に美名を欲求する病的な行為だろう。通常は、キリスト者と言えども寿老人や福禄寿に長寿・延命・健康を願って一向に差し支えがない筈である。それに、キリストは最後の敵である悪魔(罪・病気・死〉と闘って死なれたのだ。私がこれらの悪魔として『聖書』に叙述されているものを、総括して不条理と呼んでいることは、読者はとうにご存知だが、悪魔の最たるもの、不条理の最後のものが、パウロの言う通りに死なのである。この死を死なせるためにキリストは、あの若さで死んでいった。このキリストの行為は、我々の存在を死から遠ざけるためのものであったのに、その我々が早死にすることを願ったのでは、キリストに申し訳がない。キリストの若死は、我々の寿命が長くなるためであった。死は、『聖書』では、精神的な事柄でもあるし、肉体の死でもある。なるべく早く死んで、永遠の世界で長く生きれば良いなどとは、『聖書』の何処にも書かれていない。
キリスト教の愛の神は、我々が自分の長寿を祈ると、―そのご性質から考えると、その願いをかなえるために―、ただお1人で行動するよりも、福禄寿や寿老人のような天使的諸存在を巻き込まれて、どうしたら良いかなどを検討されるだろう。それが神のご性質だからである。
ピノッキオ物語の、母親のような小さな女神と、至高神や他の偉大な神的存在との関係を考える時に私は、シモンとアンデレを弟子にした時のイエスの言葉「わたしについて来なさい。人間をとる漁師にしよう」(「マルコによる福音書」1・17)を思い出す。彼らは漁師として網を打つのに馴れていた。至高神や、神仏たち、天使たち、妖精たちは、私たちや動物たちや自然の諸物が不条理の海の中で泳ぎ回っているのを救い出すために網を打っているのだ。その綱は―老子の言うように―疎にしてもらさない。ピノッキオの女神は、その大きな網の1つの目を作っている、1つの糸の結び目に過ぎないのかもしれない。しかし、その結び目が動くと、他の結び目も動き、網全体が影響される。小さな女神が、自分の行いたいことのために存在全体の協力を要請できるのだ。これが小さな、身近な神仏への祈りが、至高神や偉大な神仏への祈りと同様の結果をしばしば得る理由なのだろう。ここに、民衆宗教の神々や仏たちを巻き込んだ、本当の意味で習合したキリスト教の姿がほの見えている。
> TOP
入力:黒田良孝
入力: 黒田良孝
http://www7a.biglobe.ne.jp/~dmd-note/
http://web.archive.org/web/20051219224159/http://blog.livedoor.jp/p-3862657/
2004.4.18